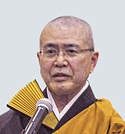縮む仏教界 「関係人口」開拓めざせ(4月25日付)
米国の世論調査研究所ピュー・リサーチセンターは近頃、仏教国の中で日本の仏教離れが最多という調査結果を発表した。それによれば、仏教徒として生まれ育った日本人は、成人になって40%が自ら無宗教を自認しているという。
なお、同センターは過去に、日本の習俗事情も重視した報告も出しており、宗教離れを相対的に理解する見解も示している。これは、日本人なら感覚的に分かることだと思う。仏教徒として生まれ育っても、それは形ばかりのもので、本人は信仰者という自覚は薄く、改めて「あなたの宗教は」と問われたので、無宗教と回答した可能性も考えられる。
従って、仏教離れと言っても、積極的に“棄教”しているわけではなく、葬儀や墓参りなどを通じて、何らかの形で仏教につながっている事例は数多い。けれども、そのつながりが希薄化したため、日本では仏教離れが進んでいるという統計として表れているのではないか。もちろん、仏教界では宗門や寺院、僧侶などの単位で、様々な取り組みを進めているのは言うまでもない。
この取り組みを進めるヒントに、地域づくりに関してよく言われる「関係人口」を増やすという考え方がある。この言葉は、地域づくりの担い手になる人々を指す行政用語として総務省などで用いられ、地方創生に関する各方面で注目されているものだ。
地域に住んで暮らす人々を「定住人口」という。一方、観光などで訪れた一過性の人々は「交流人口」である。「関係人口」とは、いわば観光以上・定住未満の人々の在り方で、その地域に多様な関わりを持つ自由な人々である。こうした人々こそ、地域づくりに欠かせない存在である。農業体験や祭礼への参加、地場産業や文化伝承でリピーターになっている人々など、「関係人口」をうまく確保して地域づくりに貢献できた成功例も数多く報告されている。
この発想は、「人口」が縮小する仏教界にも十分当てはまるだろう。寺院は檀信徒という「定住人口」のみに拘泥するのではなく、仏教の教えや行事に親しんでくれる「関係人口」の開拓にも努めるべきである。幸い仏教には宗教文化面での魅力的な社会資源を数多く有している。
そもそも日本は仏教国で、誰もが潜在的な仏教の「関係人口」なのだ。だからこそ寺院の門を開き、工夫を凝らしていけば、潜在的な「関係人口」は顕在化してくるはずだ。そうすれば、無宗教と回答した人々も再度、仏教徒だと自認し直すことになるに違いない。