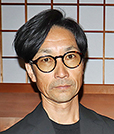「信教の自由の武器化」 変動する世界の中の宗教(4月23日付)
公益財団法人国際宗教研究所の『現代宗教2025』は「宗教の自由と政教分離」を特集している。巻頭の座談会(島薗進、駒村圭吾、松本佐保の3氏)のテーマが「現代アメリカからみる『法の支配』と宗教」であることは、日本国憲法や宗教法人法における「信教の自由」も、宗教の自由を巡るグローバルな変動を視野に入れて考える必要が出てきたことを示唆しているのではないか。
東京地裁が旧統一教会に関する宗教法人解散命令請求を認める判断を下したことで、日本国憲法が保障する「信教の自由」について改めて議論すべきだという意見が識者の間で多く出ている。本紙のいくつかのコラムでも、旧統一教会の特殊性を指摘して東京地裁の判断を妥当としつつ「信教の自由」の領域に国家が関わることの意味も考えるべきだ、といった論調が示されている。
解散命令の理由としては宗教法人法第81条1に「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと」が挙げられており、刑法・民法の区別はない。しかし国家の宗教への介入は望ましくないという懸念は当然ある。旧統一教会側も日本国による宗教弾圧だとする主張を海外で展開し、後押しする人々を集めて、政治的な圧力にしようとしている。
国内の世論動向をみると、宗教弾圧を叫ぶ一部の言論(サリン事件の際にオウム真理教に有利な発言をした海外の団体関係者も含む)は取るに足りないようにみえるが、注意を怠るべきではない。
政治的に「宗教の自由」が問題となっている例としては、ロシアの仕掛けるハイブリッド戦争への対抗としてウクライナがモスクワ系ウクライナ正教会の活動を非合法化した例がある。ロシア側はこれを宗教の自由の弾圧として国連をはじめ世界に訴え、ウクライナの現政権にとって無視できない圧力になっている。最近も、エストニアがモスクワ系エストニア正教会を非合法化したが、キリル総主教はキリスト教弾圧として早速攻撃した。米のトランプ大統領にもメッセージを送り理解を求めたが「宗教の自由擁護」が外交の柱だというトランプ政権には有効に働くとみたわけだろう。
冒頭に挙げた『現代宗教2025』の座談会では、駒村氏が「信教の自由の武器化」を指摘している。近代的なあるべき社会の理念はタガが外れつつある。その影響は日本にも及ぶ。憲法の保障する信教の自由について改めて考えるとき、世界の中の日本という視座はより重要になるに違いない。