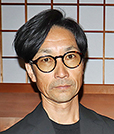バイオフィリア 核廃絶への宗教者の姿勢(11月8日付)
今年のノーベル平和賞受賞に際して、日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)の田中煕巳・代表委員は本紙の取材に応じ、「核兵器の問題は命の問題である。命を大切にする宗教者と今後も活動を共にしていきたい」という内容のことを語った(10月16日付既報)。日本の宗教者は広島や長崎で被爆体験を持つ人々から証言を受け継いできているだけに、核兵器廃絶を訴えるとき、世界でも別格の立場にあると言えるだろう。
核兵器は、大量破壊兵器としての側面が従来強調されてきた。だが、その危険性は放射線被爆を通じて、命そのものを破壊するところにある。そして使用後も放射性物質が残存し、住民の生命や自然環境を危険にさらし続ける。それが通常兵器と異なる核兵器の恐ろしい点だ。
それ故宗教には、人間のみならず生きとし生けるものの命を守る姿勢を堅持し、絶えず国際的な世論へ訴えていく義務がある。この姿勢は、どの宗教も持つバイオフィリア(生を愛好する性向)に由来するものである。バイオフィリアは死よりも生命を愛好し、生命の維持を目指す、決してぶれることはない確実な羅針盤である。宗教はいずれも慈悲や愛という形で、そうした生命肯定的な価値観に発する倫理を有し、この倫理に基づいて平和を訴えてきた。
一方、私たちはともすれば、これと反対のネクロフィリア(死を愛好する性向)にも振れてしまうことがある。その端的な現われが紛争や戦争である。紛争や戦争においてネクロフィリアは一層強化され、際限の無い報復や復讐を生む。そこにあるのは凶暴な力の支配である。それはまさに戦争がもたらすネクロフィリアの特徴であり、その最凶の兵器が核兵器なのである。
ノルウェー・ノーベル委員会は「約80年間戦争で核兵器が使われていない」と、日本被団協の授賞理由の中で述べた。しかし核実験はこの80年間に2000回以上も各国で行われており、その過程の中で核兵器は高性能になり、破壊力も増してきている。報道によれば、今回のノーベル平和賞発表後、ロシアのプーチン大統領が戦略核戦力の演習を開始したという。戦争がいったん始まると、軍事力の歯止めが利かなくなり、行き着くところは核兵器の使用にもなりかねない。バイオフィリアの生命肯定的な価値観を国際世論の基調にしていくことが焦眉の急である。その意味で、日本の宗教者は今後も核兵器廃絶に向け、一層声を上げていくことが期待される。