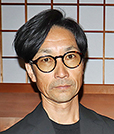多国間協力推進 今こそ宗教の叡智結集を(3月19日付)
ロシアの侵略以降、ウクライナの子どもたちの死傷者は少なくとも2500人以上に達し、5人のうち1人が近親者や友人を失った。これを発表したユニセフは、1600以上の教育施設、800近い医療施設が破壊・損壊され、子どもの犠牲者数も実際はもっと多いだろうと推定している。
ユニセフのキャサリン・ラッセル事務局長は「ウクライナの子どもたちの生活には、あまりにも長い間、死と破壊が付きまとってきた」と語る。「何よりも彼らに必要なのは持続的な平和だ」という訴えを極めて深刻に受け止めなくてはならない。一刻も早い停戦が求められる。
ウクライナだけではない。パレスチナをはじめ世界各地の紛争地域で、未来を担うべき多くの子どもたちが最悪の状況に置かれていることを私たちは認識すべきだ。
超大国アメリカはトランプ大統領の再選後、自国中心主義、なりふり構わぬ国益追求が露骨になり、これまでの国際関係を支えてきた約束事を無視し始めた。地球温暖化対策のパリ協定や国連人権理事会からの離脱、WHOからの脱退方針表明etc。「毎日何かが起きている。新鮮だ」(FoxNews YouTubeのトランプ会見に対する投稿)とトランプ支持者は歓声を上げる。DEI(多様性・公平性・包摂性)配慮否定など、米国の大企業などでも早速受け入れるところが出ている。しかし、他国との信頼関係は崩れつつある。
6日のホワイトハウスでの記者会見でトランプ大統領は「核兵器の威力はとんでもない。我々全てが非核化できれば素晴らしいことだ」と発言したと伝えられるが、現実は逆の方向に進んでいるのではと危惧される。世界は100年前に逆戻りしたかのようだ。国際協調軽視の「トランプの平和」が持続する保証は何もない。
その中でさすがに多国間協力の重要性を改めて力説する声が上がり始めている。それぞれの価値観を超えて共有できる場を探る地道な努力が最も強く求められる。
日本の宗教者も長年実践してきた宗教間対話なども、成果こそ地味だが、その中で培われた信頼関係は大きな意味を持ってくるだろう。米のバンス副大統領は政権にとって不都合な司教たちの発言についてカトリック信者に向け「執着するな(真に受けるな)」と言ったが、離合集散の混沌とした世界の中で宗教者がなすべきは、権力者に忖度せず、宗教の叡智を結集し、それを発信することだ。
宗教の立場から多国間協力を実践し、危機に瀕した世界を救う努力をさらに重ねてほしい。