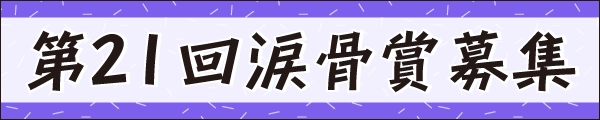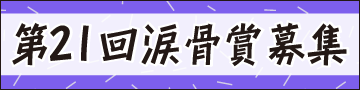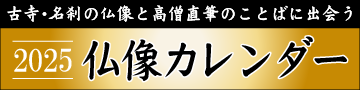効率社会へ無言の拒否? 静かに続く遍路への関心(6月14日付)
弘法大師空海ゆかりの八十八ヵ所霊場を巡る四国遍路に、コロナ禍で激減していた巡礼が戻ってきたようだ。今年は功徳が3倍になるという逆打ちの年(うるう年)でもあり、例年に近い水準にまで回復しているという。
日本人は信仰心が薄いといわれる。だが、パワースポットやスピリチュアルが日常語になって久しく、一方で分断社会といわれる世相の行く末に懸念が募る。そんな時代にあって、社会現象化した感もある四国遍路が発するメッセージは何か。遍路道の各所に巡礼の休憩所を造る「四国八十八ヶ所ヘンロ小屋プロジェクト」に長く関わってきた梶川伸氏は「遍路には、戦後日本を支えてきた基本的価値とは正反対の価値観がある」という。示唆に富む指摘である。
四国遍路は例年約10万人の巡礼があるとされるが、2020年のコロナ禍で一時は6割以上も減った。だが、今年のゴールデンウイークはいつものにぎわいを取り戻し、外国人が目立ったという。
巡礼の方法は観光バスとマイカーが大半だが、マスメディアなどを通し流布される歩き遍路の情報が四国遍路のイメージを形成しているようだ。歩き遍路は1200㌔の遍路道を霊場から霊場へと、苦しくてもとぼとぼ歩く道中で地域の自然と風土に触れ、地元の人々に人情厚く接待される。そこに、現代の「無縁社会」が見失った緩やかな連帯意識が生まれる。宗派とは関わりなく「お大師信仰」を共有していることも、心が結ばれやすい要因の一つだろう。
四国遍路は時代により、その様相を変えてきた。古くは仏道修行の場として、また大衆化した江戸時代からは「お接待」に象徴される遍路文化が生活困窮者のセーフティーネットの役割を担ってきた。
社会福祉が整備されたため、今の遍路は人との交わりを求め、また癒やしや人生の意味を問い直す自己確認のため、などの動機が特徴とされる。信仰を挙げる人が少ない半面、誰もが参加できる多様性は一神教には見られない仏教ならではの特性だろう。
年齢層では定年世代と若者が多く、階層別では中間層が中心とみられる。戦後日本を築いた経済効率・成長至上主義を前に立ちすくむ若者や、そのくびきから解放され、戸惑いつつもゆとりある余生を切望する人間像が浮かぶ。
近年、四国遍路を世界遺産に、という運動が熱を帯びている。だが、効率を求めるのではなく、結願までひと月以上の時間をかけて、自己の生の意味を心静かに考えたい遍路の存在を忘れてはなるまい。