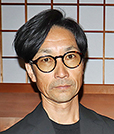着床前診断の審査 命の課題に宗教界も発言を(12月13日付)
重篤な遺伝性疾患があるかどうかを受精卵段階で調べる着床前診断(着床前遺伝学的検査=PGT-M)の実施が増えている。結果次第では“命の選別”にもつながる生命倫理的問題をはらむだけに、十分な論議が必須だ。
体外受精後に卵を検査し、病気がないと判定されたものを母胎に戻す診断は、親の希望を基に実施したい医療機関が日本産科婦人科学会に申請し、個別に審査される。障害や病気の子は産まないという優生的選別になる懸念から1998年以来、慎重に進められてきたが、2022年に対象疾病を拡大する条件見直しが行われた。
その結果、申請の幅が広がり、昨年1年間には72件に。そのうち58件が承認、3件が不承認、11件が審査継続・取り下げとなり、承認件数はこれまでで最多となった。過去には審査結果は明らかにされてこなかったが、昨年は「ミトコンドリア病」や筋ジストロフィーの一種、初例の眼球のがんなども認められた。
診断結果で妊娠をどうするかは、医療機関の関与を離れて「母親」側の判断ではあるが、医師の「宣告」が大きな影響を及ぼすことは十分考えられ、学会加盟の病院などではしっかりした遺伝カウンセリングなどを心がけている。
しかし、妊娠後に母体の血液から胎児にダウン症などの疾病があるかを調べる新型出生前検査の場合を見ても、現実には「陽性」と診断されたケースの多くで人工妊娠中絶が選択されていることが知られる。この着床前診断でも、診断後の経過、結果は不明だ。
このことからスタート時点の診断における厳格さが求められるが、現況では審査基準や機関は学会など民間の自主的規則に委ねられている。そのため、学会などからも公的審査制度や審査ルールの必要性が言われている。
審査基準で一律に病名を挙げて法令化するのは、それこそ優生思想が入り込む危険性が大きい。だが個別のケースにどう対応するか、どの専門機関が責任を持って関与するかは重要な課題だ。
イギリスでは以前から法律に基づいた公的機関が認可や監督をしており、韓国やフランスなど公的規制がある国はたくさんある。日本では、新型出生前検査について国が専門委員会を設けているが、着床前診断など全般的にはまだまだであり、国民的論議を踏まえて対応が求められる。これから生まれてくる命に関わる問題である以上、医学的専門的立場とは別に「いのちの専門家」であるはずの宗教界も無頓着であってはならないだろう。