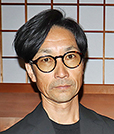勤労感謝の日 仏教における労働の意義(11月20日付)
11月23日の「勤労感謝の日」について、国民の祝日に関する法律は「勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう」と説明している。天皇が収穫物を神々に供えて感謝し、自らも食する「新嘗祭」の日に当たり、これが戦後、日本国憲法制定に伴い祝日とされた。憲法は、国民の三大義務として教育の義務、勤労の義務、納税の義務の三つを定め、第27条に「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う」とあって、勤労の権利と納税の義務を一体的に位置付けている。
人は人生の多くの時間を勤労に費やし、働くことで生活の資を得ていることからすれば、勤労は人生そのものと言ってもよい。しかし仏教では釈尊以来、出家者たる僧侶が労働に従事することはなかった。世俗の生活を捨てて仏道修行に専念する僧侶は、農耕によって生き物を殺生することを避け、最低限の生活に必要な衣食は托鉢によって施主から得た。
原始仏典のスッタニパータに有名な逸話がある。田を耕すバラモンが、食を受けるために立つ釈尊にこう告げた。「道の人よ。わたしは耕して種を播く。耕して種を播いたあとで食う。あなたもまた耕して種を播いたあとで食え」と。釈尊は「わたくしもまた耕して種を播く。耕して種を播いてから食う」と答え「信仰が種であり、苦行が雨である。知恵が軛と鋤である」と言った。身口意を慎む覚者の生活法は甘露の果実をもたらし、あらゆる苦悩から解き放たれるものであって、報酬として得たものを食べるのではないと断言する。
出家道場である僧堂はこの古き伝統を伝えている。現代の僧侶もまた化主として檀信徒から布施を頂き、生活の糧としているという意味で同じ伝統の中に生きている。僧侶のこうした日常を考える上で「一日作さざれば一日食らわず」の句を残した唐代の禅僧・百丈懐海の存在は大きい。
高齢の百丈禅師が耕作に従事するのをいたわり、弟子たちが農具を隠したところ、禅師は部屋に入ってしまい、食事を取らなくなった。心配した弟子が尋ねた時の答えがこの一句である。
百丈禅師は大乗・小乗の戒律を集成し、自給自足を志向する叢林の規範を定めた。生活を自立させることで精神の独立を確保したところに画期的な意義があるといわれる。行住坐臥の全てを仏作仏行として尊ぶのを基本的な規律とすることは、世間と同等の日常生活を送る現代の僧侶・寺院においても尊ぶべき規範として意義付けられるのではないだろうか。