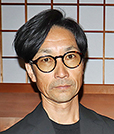災害ボランティアの課題 現地のコーディネートが要(11月13日付)
災害ボランティアの在り方を考える公開講座がこのほど日本社会事業大専門職大学院で開かれ、現場に根差す支援や福祉の関係者らの突っ込んだ論議でボランティア活動の意義と課題が示された。
中でも宗教者を含めて被災地で実際に活動する支援者と被災者をつなぎ、善意の奉仕と需要とをコーディネートする災害ボランティアセンター、社会福祉協議会(社協)の役割や現場での問題点が焦点に。講師で全国の現場で長年支援のバックアップを続ける防災専門家の園崎秀治氏は、あくまで民間として公助にはできない働きを担う現地のボランティアセンターや社協にも力の限界があり、広域の外部の助けを受け入れる「受援力」がカギだと解説した。
参加した各地の支援関係者からはボランティアが陥りがちな陥穽についても指摘が相次いだ。行きやすい場所に集中する、長いスパンの支援を度外視して自らの都合だけで撤収するなど。「自分たちの価値観を押し付けないでほしい」と訴えた北陸地方の社協職員によると、経験の多い支援グループが全国あちこちの被災地に赴いた実績をひけらかし、地域の事情が異なるのに活動の方法などを決めつけてかかることもあるという。
社協との連携が必須ではないが、ボランティアが「する側」のためではなく、基本的には苦難にある被災者のためにあるという自明の理を踏まえれば、現地の声に耳を傾けるのは重要であり、これもコーディネートの課題だ。別の社協職員は、人々への寄り添いは平時からのソーシャルワークが基礎であり、災害時にもその普段の福祉の確保が大事だと指摘したが、それも地域の事情を平時から知り尽くす立場だからこそだ。
にもかかわらず、例えば能登半島地震でも社協職員全員が自らも被災して疲弊しながら昼夜調整に働いているのを無視して交渉を避け、「自主的」「草の根」という言葉をはき違えて勝手に振る舞う向きがあるのは残念だとの声を現地で聞く。真に被災地に向き合う姿勢を持った多くの宗教者は、まず当事者のニーズを聞き、あるいは現地で支援をする地元の人たち、地元の宗教者と連携してきめ細かい動きを見せている。
彼らが「ボランティア」という言い方さえしないのは「人は人に尽くすのが当然の生き方」との信仰からだ。「あなたがしてほしいことを他の人にもしなさい」という各宗教に共通する「黄金律」もそれだ。苦難の被災地で“布教”はもちろん、自らの活動をPRなどしなくても地元に密着した真摯な行いでその心はしっかり伝わる。