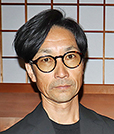偽・誤情報の蔓延 宗教界はどう対処するか(10月4日付)
SNS時代になって、一つ一つの情報の信頼性を見極めるのが非常に困難なことが増えた。命に関わるようなことに加え、もともと決定的証拠を示すのが困難な事柄には、フェイクニュースや陰謀論が生まれやすい。
典型的な例はワクチン問題である。子宮頸がんを防ぐワクチンや新型コロナウイルスのワクチンに関しては、多くの陰謀論やフェイクニュースがネット上に飛び交っている。同じ反対意見でも、臨床実験などに基づいた真面目な意見と区別するのは、専門的知識がない人にとってはけっこう難しい。
宗教に関わる言説も、真剣に宗教の問題を考えた発言と、炎上目当てのいい加減な発言を、誰もが見分けられるわけではない。理由の一つは、宗教の語りには逆説的表現が交じることが珍しくないためだ。
SNSが広まる以前だが、宗教家と一般の学生とが対話する会議で、カトリックの神学者が「人を幸せにするのが宗教ではない」と発言したことがある。信仰の厳しさを述べた言葉であったが、ここだけ切り取れば、宗教は人を不幸にすると読まれかねない。この箇所を宗教批判に使おうと、SNSで拡散されたらどうなるか。
宗教の言葉は語られる場所や語る人に依存する割合が高い。激しく叱責するような言葉でも、日頃思いやりのある宗教家として認識されている人からであれば、それが実は励ましであると受け止めることができる。多くの信者がいる中で言われた言葉か、二人だけの対面状況で言われた言葉か、その環境の違いも言葉のニュアンスに影響を与える。
SNSでの言葉のやりとりは、匿名が多く、コンテキストも読み取りにくい。言葉だけに反応すれば互いの価値観のぶつかり合いになってしまう。ここに各人の認知バイアスが絡まるから、理性的な議論、背景を読み取っての議論は非常に困難になる。
だから宗教の話は対面を主とすべきだというのはもっともな意見であるが、少なくとも若い世代ではSNSが情報交換の主流になっているというのが実際である。それに現代では対面状況の設定自体が容易ではない。
宗教についての極めて根拠が乏しい主張、相当偏ったものの見方が蔓延する時代にどのように対処するのか。大きな寺社なら独自に対処の方法を考える人材がいるかもしれないが、中小規模の寺社では、なかなか困難である。宗派の枠にこだわらず、それこそSNSを利用して、広く意見を交換する場を増やさなくてはなるまい。