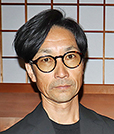ロボット社会 科学の未来は人間が決める(9月27日付)
ロボットの起源は神話や伝説の中にあり、やがて機械仕掛けで動く人型のロボットというイメージが19世紀に入って定着する。ロボットは今や人間のパートナーと言ってもよい。一方で、AIの搭載によって、ロボットが人間を超える時点が来ることへの危惧も語られる。だが、どれほど時代や科学技術が進歩しても、ロボットを操る人間の心を健全に育てることが人類にとって最重要の課題であることは変わらない。
昭和末期に登場したロボットは、未熟だがどこか愛嬌を感じさせる動きが愛玩物としての親しみを感じさせた。1996年に二足歩行を行う人間型ロボットをホンダが開発し、99年にソニーが犬型の「AIBO」を発売して話題となった。今やロボットは産業、医療、文化、宗教、戦争など様々な分野で必要とされるハイテク機器として人間社会に存在の場を拡大している。
ロボットと人間の関係について作家で生化学者のアイザック・アシモフが50年にロボット三原則を打ち出している。SF短編集を通して世に広まったもので、第一原則は「ロボットは人間に危害を加えてはならない」▽第二原則は「ロボットは人間に与えられた命令に服従しなければならない」▽第三原則は「ロボットは第一および第二原則に反しない限り、自己を守らなければならない」――とある。
三原則を読む限り、ロボットを開発する人間に課せられた倫理原則というべき内容である。こうした基準の原則化が意味するのは、人間とロボットとの関係が、もはや人間生活を豊かで便利にしてくれる愛すべき相棒としてあるのではなく、急速に進歩を遂げるテクノロジーを追いかける人間の側の期待と不安を暗示するものになっているということだろう。
ロボットのいる風景は日常化している。レストランのフロアを滑るように動いて料理を運び、食器を回収するロボットを見かけることも珍しくはない。文明を操る人間は、生活の利便性と効率化を求めて様々な技術を開発してきた。ロボットの進化は人間生活の進化と共にある。
しかし人間には、AIの発達やロボットの活躍に目を奪われるだけでなく、生みの親として、その行く末をしっかり見守る義務がある。ちょうど「鉄腕アトム」で、アトムを作った天馬博士がアトムをサーカスに売り飛ばしたとき、引き取り我が子のように見守ったお茶の水博士のように。科学の健全な進歩は、そうすることで維持できるのではないだろうか。