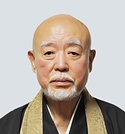発掘調査成果から探る山科本願寺の実像(1/2ページ)
京都市埋蔵文化財研究所調査課担当係長 柏田有香氏
東山の大谷本願寺を追われて以後、各地を転々として布教活動を行っていた本願寺8世蓮如は、文明10(1478)年、現在の京都市山科区西野の地で山科本願寺の造営を開始し、悲願であった本願寺再興を遂げた。山科本願寺は壮大な規模と財力を誇り、一時は将軍家や有力武家をしのぐほどの繁栄ぶりであったとされる。しかし、蓮如の死後、本願寺10世証如の代の天文元(1532)年に管領細川晴元率いる軍勢によって攻撃され焼け落ち、大坂へ移転することとなった。
山科本願寺の寺域は土塁と濠で囲まれ、阿弥陀堂、御影堂をはじめとした主要堂舎の置かれた「御本寺」、有力末寺の坊舎が置かれた「内寺内」、門徒の居住区などがある「外寺内」の三つの郭で構成されていた。阿弥陀堂と御影堂を並立させ、前庭を広くとる配置は山科本願寺が祖型とされ、現在の本願寺系各寺院に継承されている。
現在は遺跡中心部を国道1号線と東海道新幹線が東西に貫く。地上にある山科本願寺の痕跡は国道1号線の北側にわずかに残る土塁や濠の一部と「外寺内」に位置する蓮如上人墓など数えるほどである。山科本願寺で初めて発掘調査が行われたのは新幹線敷設に伴う1962年の立会調査である。その後、現在までに22回の発掘調査と多数の試掘・立会調査が行われている。特に2011年度からは遺跡保存を目的として寺域中心部で継続的に発掘調査が行われ、重要な発見が相次いだ。主要堂舎の配置をある程度復元することが可能となったことに加え、寺を囲う土塁についてもその構造や構築時期についての新知見が得られた。その成果を受けて、16年には寺域中心部が国史跡に指定された。以下では、それら発掘調査の成果を紹介し、山科本願寺の実像を探りたい。
山科本願寺の外郭を囲う土塁と濠については、これまでに複数の箇所で調査が実施されている。
「御本寺」南西角の調査では、土塁の高さは5~6メートル、基底部幅18メートル、上面には幅約2メートルの平坦部があり、斜面の最大傾斜角度は約45度であることが分かった。ここでは濠の跡も見つかっており、幅5~12メートル、深さは1・5~4メートルあったが、土塁が途切れている部分で特に濠の規模が大きくなっていることが判明し、当初から土塁が存在しなかった可能性が高い。また、この地には近年まで「オチリ池」と呼ばれた池が存在した。史料に記された天文元年の焼き討ちの際の侵入口「水落」に音が似ており、さらに土塁が切れていたとすれば、この南西角が侵入口であった可能性が高い。
「御本寺」西辺部の調査では、土塁高さは約4メートル、基底部幅約8・5メートル、斜面の最大傾斜角度は約40度、濠の幅は10~11メートルあることが分かった。南西角の土塁と比較すると規模はやや劣るものの、土質の異なる土を使い分けて崩落を防ぐ積み上げ方や、石組みの暗渠排水溝の敷設などの構築方法は共通し、高い土木技術があったことがうかがえる。
同じく「御本寺」西辺で2011~12年度に実施した調査では、土塁の構築に関して新たな知見が得られた。調査では地中に埋没していた土塁が見つかり、さらにその土塁の下から粘土採掘のための土取り穴が見つかった。穴からは、山科本願寺期の15世紀末~16世紀初頭に位置付けられる土器が多量に出土したことから、この土取り穴が埋められた16世紀以降に土塁の土が積まれたということが分かった。つまり、山科本願寺の造営当初は土塁が存在せず、明応8(1499)年に没した蓮如の死後に造られた可能性が高いということが判明したのである。
土塁が山科本願寺造営当初には存在しなかった可能性についてはすでに真宗史の草野顕之氏による指摘がある。草野氏は山科本願寺の堂舎に関する記述がある『御文』や『空善聞書』など複数の史料から、創建期に造営された堂舎とそれ以後に追加造営された堂舎の復元を試み、その結果、創建期の山科本願寺は本寺本願寺部分の阿弥陀堂、御影堂をはじめとした幾つかの堂舎のみが造営され、その部分は土塁ではなく築地塀で方形に囲まれていた。第二郭(内寺内)、第三郭(外寺内)は蓮如の没後、本願寺9世実如期に形成された。土塁の形態をとる時期については、大きな普請が行われたことが史料に記された時期を勘案し、永正年間(1504~21)ではないかと推測している。これは、土塁の構築時期が16世紀代であるという考古学的成果とも矛盾しない。