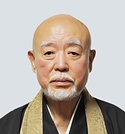アメリカでの日本仏教の影響と貢献(2/2ページ)
武蔵野大教授 ケネス田中氏
ママ パパ まだあるよ。忘れてたよ。ほらあの話な。ミーが小さい時からいつもママがミーに話してくれたあの話よ。仏さんの話よ。あの話ちゃんと覚えとるから安心してよ。オーバーシーへ行っても仏さんはミーについてくるんだったなあ。ミーさみしくないよ。仏さんがミーを守っていてくれるんだものなあ。
あの話、覚えとるからママもパパも心配せんでもいいよ。では行ってくるよ。ママもパパも大事にしなさいよ。グッバイ」
何と心を揺さぶる手紙であろう! この手紙は、英語が母国語である青年にも仏教が心の不安の支えとなっていたことを語る。
ちなみに、この兵士の手紙とも関係するが、日本仏教の貢献として一つの例を挙げておきたい。それは、浄土真宗本願寺派の米国仏教団(Buddhist Churches of America)が成し遂げたことである。1987年、この教団が主催する大学院大学を通じて、教誨師資格の授与が、「軍隊の仏教チャプレン」として初めてアメリカ政府に認められた。当時、このことは一般メディアによって大きく取り上げられた。この例が示すように、133年の歴史を持つアメリカの日本仏教は、仏教全体を代表し、社会の影に対応する教誨師制度などに関して、指導的な役目を果たしてきたのである。
日本でもおなじみのレオ・バスカーリア教授の『葉っぱのフレディ』という短い絵本は、アメリカで大ヒットし、何百万冊も売れた。日本語訳も脚光を浴び、学校で読んだという日本人も少なくない。このシンプルな子供向けのような絵本が成功した理由に、死というテーマを真正面から扱ったことが挙げられる。
死は、アメリカでは、タブー視される傾向があるということは既に述べた。何故なら、仏教の「生死」という教えが示すような「死とは生まれるということと一体であり自然なことである」という考えとは異なり、「非自然的である」という考え方が主流だからである。このような背景がありながらも、葉っぱを擬人化して分かりやすく、受け入れやすく死を語ったことに、子供たちも興味を持ったが、それ以上に多くの大人が納得し感銘を受けたのである。
実は、この本には「仏教」という言葉すら出てこないが、私は、最初読んだ時から内容が非常に仏教的であると感じていた。そこで、著者のバックグラウンドを調べたところ、育ちはカトリックであったが、大人になって一時日本の禅宗のお寺に在住し、仏教に強く影響されたということが判明したのである。その時私は、著者のバスカーリア教授に仏教の影響が実際にあったことを知って、納得することができた。そこで、同書の仏教的な考えと思われる一部を紹介しよう。
「『ぼく、死ぬのがこわいよ。』とフレディが言いました。
『そのとおりだね。』とダニエル(友だち)が答えました。『まだ体験したことがないことは、こわいと思うものだ。でも考えてごらん。世界は変化し続けているんだ。変化しないものは、ひとつもないんだよ。春が来て、夏になり、秋になる。葉っぱは緑から紅葉して散る。変化するって自然なことなんだ。』……
『死ぬというのも、変わることの一つなのだよ。』変化するって自然なことだと聞いて、フレディはすこし安心しました。」(『葉っぱのフレディ―いのちの旅』みらいなな訳)
このように、ダニエルの説明は仏教で説く「諸行無常」に等しい。そして、全てが変化するが、変化というものは自然なことであると、さらに教えを深める。ダニエルは、自分の死を受け入れさせ、死に対するフレディの苦悩を和らげた。このような考え方は、著者が仏教に影響されて、より鮮明になったものだと思われる。
若さ・楽しさ・進歩・自由などを掲げるアメリカ社会でさえも、人間社会である限り「影」が潜んでいることは当然である。しかし、アメリカ社会では、老い・死・苦悩・失敗・格差などの影に面と向き合い、それに対応する論理や思想が比較的弱かった。そこに到来した仏教は、特に死という影に光を照らし、死への不安や恐怖が転換され、バネとなることを主張してきた。これこそ、あまり知られざるアメリカ社会における日本仏教の貢献の一例なのである。