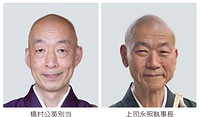真溪涙骨の前半生と七里恒順の感化(1/2ページ)
龍谷大教授 中西直樹氏
「中外日報」を創刊した真溪涙骨(本名「正遵」、1869~1956)は、自分の名前が表に出ることを極端にきらい、自らの経歴を語ることもほとんどなかった。このため、涙骨の前半生のことはよく分かっていない。
2019年10月18日付の本紙で涙骨の生誕150年を記念して「中外日報」創刊までの足跡について記したが、その後、かなりの点が明らかとなったので、再び涙骨の半生について論じてみたい。
今回、特に明らかになったのは、青年期の短い間であったが、涙骨が七里恒順(1835~1900)のもとで学び、大きな感化を受けたことであった。恒順は、明治期を代表する名僧として知られ、自坊・博多万行寺(真宗本願寺派)において多くの人びとを教化した。数多い恒順の門下生のなかでも、涙骨はひときわ異彩を放つ存在でもあった。
涙骨は、越前国敦賀藩田結浦(現福井県敦賀市田結)の本願寺派興隆寺に、同寺住職真溪正善の長男として生まれた。父正善は養子として若狭から入寺し、母が興隆寺の出身で月輪みなといった。
長じて涙骨は、本願寺派普通教校(龍谷大学の前身校の一つ)に入学したが、悪戯が多くまもなく退学となった。普通教校の同窓生名簿には「敦賀郡田結村 月輪正遵」と記されており、当初は母方の姓を名乗っていたようである。
普通教校退学後、涙骨は恒順が自坊に開いていた私塾・龍華教校に転じた。龍谷大学大宮図書館所蔵『龍華教校入校名簿』には「福井県越前国敦賀郡田結浦 興隆寺衆徒 月輪正遵 明治十八年四月二十八日入」との記載がある。涙骨の転校は、普通教校の生徒取締で恒順の門下生でもあった多田賢順が仲介したものと推察される。
しかし、涙骨は龍華教校でも僧侶修行に身が入らず、手刷り新聞を発行するなどして、恒順に叱正を受けて退校したとされる。
常光浩然『明治の仏教者』によれば、その後の約10年間、涙骨は各地を放浪したようであり、詳細は不明である。
ところで、当時、東京では本願寺系新聞「奇日新報」が発行されていた。「奇日新報」は本願寺派寺院の出身で、「朝日新聞」の東京支局通信主任だった干河岸貫一が中心となり、本願寺派の関係者・関係団体が賛成社員となって発行を支えた。なかでも最も熱心に支援したのが恒順であった。干河岸は、後に回想録『書窓漫題』のなかで次のように記している。
「奇日新報の発行に就ては意外に本派有志の賛助を得たり発行部数多からさりしか常に一千部を出入したり殊に筑前の万行寺七里恒順師の如き余僅に面識あるに過されとも師は特に手簡を送り筑前一円の師か門下の僧侶を勧誘し数十の購読者を周旋せられしのミならす其代金をも取纏め郵便為替を以送付せられ頗る厚意を以奇日新報の発達を助けられしは師を以第一とす」
この「奇日新報」には、涙骨の寄稿文を散見する。例えば、1886年5月25日付同紙に遊学中に貸与した書籍の返却を求める広告を出している。そこには「福井県越前国敦賀郡田結浦 月輪正遵」と記載されており、この頃までには自坊に帰っていたようである。その後も、敦賀や京都の状況について、たびたび「奇日新報」に寄稿している。また89年10月に寄せた一文では、「奇日新報」のような通仏教的新聞の必要性を説き、仏教者がこうした新聞の発行を支えるべきことを訴えている。
「奇日新報」は、本願寺派からの経済的支援を受けて刊行されたが、一般紙の記者を長年つとめてきた干河岸の編集方針もあって、仏教界を取り巻く動向が広い視点から報道されていた。ところが、経営は苦しく、兼務する朝日新聞記者の仕事が忙しくなった干河岸は、89年3月末に「奇日新報」の経営を譲渡し、発行元が東京から京都に移った。
《宗教とAI➁》ブッダボットで変わる仏教 亀山隆彦氏2月12日
一、 筆者は日本仏教専門の仏教研究者だ。特に古代~中世の日本密教の実態解明を目標に研究を続けている。近年、その作業を通じて、ある理解に到った。それは日本仏教僧が高度な思想…
《宗教とAI➀》人間中心主義と異なる生命観 師茂樹氏2月2日
カトリック教会の問題意識 人工知能(AI)の普及によって、様々な社会問題が指摘されるようになってきている。宗教の世界でも、AIについての話題は事欠かない。 そのような中、…
開山1300年の勝縁に寄せて 横田隆志氏1月29日
長谷寺の開山 真言宗豊山派総本山長谷寺(奈良県桜井市)は、2026年に開山1300年を迎える。長谷寺の御本尊である十一面観世音菩薩は、現世・来世の願いをかなえる霊験仏とし…
第21回涙骨賞〈選考委員選評〉
- 本 賞 藤井麻央氏「泡沫の小集団・信徳舎の活動とその特質」
- 奨励賞 道蔦汐里氏「『宗教2世』をめぐる用語と意味の変遷」
- 奨励賞 岩井洋子氏「京都学派における天皇論の系譜―転換期の克服と『媒介者』としての天皇―」
涙骨賞受賞者一覧
長らくご愛顧を賜りありがとうございました。(2025.10.1)