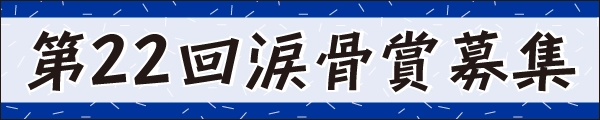過疎化対策としての他出子世帯への着目 ― 過疎地寺院問題≪2≫(2/2ページ)
大谷大准教授 徳田剛氏
その結果として分かってきたことは、両調査地のような都市部との距離が比較的近いところにある地域では、他出子世帯の多くが郷里から近い距離(自家用車で30分~1時間以内)に住んでいて、親の生活サポート(買い物、通院など)や葬式・法事などの理由で、数カ月に1度、あるいはそれ以上の頻度で帰郷している世帯が少なくない、という点であった。
もちろん、頻繁に帰郷すること自体が緊密な寺檀関係を保証するわけではなく、あくまで家庭の用での帰郷であって、寺院との接点が生じないケースも多い。とはいえ、比較的若い世代が郷里に戻ってくる機会があるということ自体は、アプローチに工夫は必要だが「まだ取り組みようがある」ということでもある。
居住地と郷里を行き来する他出子世帯との間でいかにして「お寺とつながる」「お寺を支える」ような関係性を作っていくことができるか。言うは易しだが、有効策を案出し実行することは容易ではない。一番取り組みやすいのは、これまでの伝統的な仏事や祭事をベースにして、移動する他出子世帯に働きかけることである。
だが、地方で行われている檀信徒への教化事業の多くは農業従事者が大半を占めていた社会状況で営まれてきたので、伝統行事や仏事の開催時期が(3~4月や11月以降など)農閑期に設定されることが多い。浄土真宗の重要な仏事の一つである「報恩講」も11月から1月にかけて各地で行われるが、概ね平日日中を含む数日から1週間にかけて行われることが多いようである。しかし、最近では第3次産業(商業・サービス業など)の従事者が多数を占めるため、地元在住者でも休日(土日祝日や店舗等の定休日)にしか行事に参加できない場合が少なくない。地元を離れた人たちにとっては、ここに移動コストを加味しなければならないのでなおさら参加しづらく、こうした伝統行事や仏事の維持・継承は難しくなるだろう。若い世代の仏教への関心低下、といった要因にとどまらない、検討すべき点である。
我々の行った調査の結果からは、盆・正月期の行事や近親者の葬儀の際には、在地住民、他出子ともに帰郷してそれらに関与していることが明らかになった。とすると、他出子世帯と寺院の接触機会が多い盆・正月期に若い世代を意識した行事・イベントを開催する、葬儀や重要な法事の際の法話や雑談などに工夫を施して他出した若い世代に積極的に働きかける、といった取り組みがまずは考えられる。
また、年忌法要などの伝達について、これまでなら住職と檀家が顔を合わせた際やお堂内の掲示などで伝達できたために積極的に行ってこなかった、という地域や寺院も調査先では見受けられた。他出した人たちと寺院関係者が接触する限られた機会なので、そのような法要のご案内を寺報やイベント案内などと併せて他出子世帯に届ける、などの取り組みも有効であろう。
以上が、一連の調査の結果から導き出された、他出子世帯への働きかけを中心とした過疎化対策の概要である。とはいえ、これらは限られた調査地域の比較検討の結果に過ぎず、すべての過疎地域の寺院に有効な策というわけではない。とりわけ、都市部から遠く離れているような地域では、いったん若い世代が他出してしまうと、現住地で生活基盤を築いてしまってほとんど帰郷せず、寺院との接触機会の減少や家じまい・墓じまいなどによる寺檀関係の途絶も生じやすい。
また、過疎地対応じたいは多くの宗教団体にとって共通の課題ではあるが、地域ごとの地理条件、集落ごと・寺院ごとの前提条件、各宗派の教義や組織体制の違いなどによって、問題の現われ方は実に多様である。この問題に関する、各教派での取り組みについての出版物や新聞・雑誌での記事も増えてきている。それらの知見からも大いに学びつつ、過疎地寺院のあり方について検討を続けていきたいと考えている。