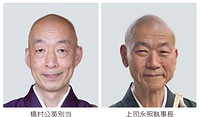新・往生論―日本浄土教の脱‐神話化のために(2/2ページ)
早稲田大法学学術院教授 守中高明氏
しかし、ここにこそ現代の浄土宗が陥っている最大の陥穽がある。「現実/神話」という二項対立を認めたうえで後者の意義を強調することは――それがどれほど善意からなされるにせよ――、結局はみずからの宗教としての現実的無力さを認め、その価値を限界づけることに帰着する。その立場は、いわば科学的知と宗教的知とのあいだに境界線を引き、その境界線の内部における「主観的事実」(清沢満之)としての宗教の営みの自由を――あたかも「言論の自由」を主張するように――権利として主張するにとどまっている。
だが、はたしてそれでよいのか。宗教的知の可能性はそのような限界内にとどまるものなのか。否、法然が最高度の知を鍛えあげたすえに称名念仏にその教えを集約し、「凡夫往生」を約束したとき、そこで目指されていたのは想像的慰藉ではまったくない。そうではなく、阿弥陀仏の名を称えるという究極の易行のうちに賭けられていたのは、衆生の生の現実の総体であり、そのリアリティを根本から変革するというまさに実践的な目的であったはずだ。
「往生」という概念を、法然はいったいどのような歴史的‐社会的文脈の中で説いたか。法然が目の前にしていたのは、「六道輪廻」という観念形態、すなわち「地獄」「餓鬼」「畜生」「阿修羅」「人」「天」の六つの世界へつぎつぎに生死を繰り返しそこから逃れることができないというオブセッションに囚われている人々、とりわけ天台宗的な修行に耐えることもできず戒律を守ることもできないがゆえに、つねに「地獄へ墜ちる」というリアルな恐怖に苛まれていた庶民階級の人々である。彼ら/彼女らは、『往生要集』の源信が構築した平安的パラダイムにおける「浄土」の理想を知りつつ、しかし、平安貴族たちや鎌倉武家政権下における豪族たちのように富の力によって寺に寄進することも「造像起塔」を競うこともできず、したがってその見返りとしての救済を期待することもできなかった。その数知れぬ庶民たちに対して法然は、阿弥陀仏の「普く一切を摂」する「平等の慈悲」を断言し、「たゞ仏のちからをたのみたてまつる」「他力」の教えを説き示した。それは当時の庶民たちにとって、その生を呪縛し苦悩させているイデオロギーとオブセッションからの解放をもたらしてくれる救いの一撃であった。その教えの効果は、まさに社会の現実的秩序に働きかけ、それを組み替える力をそなえていたのである。
法然が約束した称名念仏による「往生」とは、その意味において、今日の私たちが考えがちであるような精神的ないし想像的ないし心的な領域における出来事ではない。それは「現実/神話」「実在/非実在」という二項性に分割される以前の世界構造に属している。だとすれば、現代において私たちが「往生」を語るとき、私たちはその出来事をどこに位置づけるべきか。中世日本の衆生にとってリアルであったのとまったく等価な「往生」の時間と場所――それが死後ではないことは、もはや明らかだ。今日、私たちは誰も「六道輪廻」などという観念形態に縛られてはいない。だがその一方で、それと同じ、しかしそれ以上に強固な不可視の観念形態によって私たちは拘束され、隷属化されているのではないか。それゆえ、今日「往生」を語る必然があるとすれば、それはただ浄土の教えがその抑圧的観念形態をあばき、そこからの自由の道を切り拓くかぎりにおいてのみである。
称名念仏が決定的に重要なのは、まさにそれゆえである。「帰依―無限者に」という行為遂行的発話の反復において私たちはなにを経験するか。それは、みずからのうちに無限への開かれを見出すことであり、その開かれにおいて「大慈悲」という根源的情動に刺し貫かれることにほかならない。そのとき私たちは、一切衆生を捨てることのない無限の包摂にして絶対的な迎え入れの場、すなわち浄土と出会っている。その出会いこそが「往生」と呼ばれるべき瞬間なのであり、その瞬間を繰り返し経由することは、私たち衆生をあらゆるイデオロギー的な負の束縛から解き放つだろう。〈今‐ここ〉の生を留保なく肯定する力能の意志による諸力=衆生の能動的生成としての「往生」――今日の浄土教に求められているのは、その場面への覚醒である。