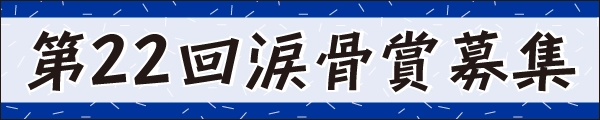憲法と皇室典範(1/2ページ)
創価大法科大学院教授 藤田尚則氏
平成28年7月13日、今上天皇が「生前退位」を望んでいるとのNHK報道があり、8月8日には天皇によるその真意を語る「お気持ち」表明が行われた。これを受けて10月には内閣官房に「天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議」が設置され、有識者へのヒアリングなどの議論が行われた後、平成29年6月9日、国会において「皇室典範」の特別法として「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」が成立した(平成31年4月30日施行)。特例法2条は「天皇は、この法律の施行の日限り、退位し、皇嗣が、直ちに即位する」と規定し、3条及び4条で退位後の天皇は「上皇」、退位した天皇の后を「上皇后」とすると定めている。これにより平成31年4月30日に天皇が退位し、翌5月1日に皇嗣たる皇太子が新天皇に即位することとなった。
「日本国憲法」1条は天皇を日本国の「象徴」とし(元首でも君主でもない)、その地位は「主権の存する日本国民の総意」に基づくと規定し、2条は「皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する」と規定し、皇位の世襲制を採用している。ここにいう「皇室典範」は、日本国憲法100条2項の規定に基づいて第91帝国議会において日本国憲法を施行するために必要な法律として、昭和22年1月16日に成立した法律である(昭和22年5月3日施行)。
「大日本帝国憲法」(「明治憲法」)と同時に制定された明治22年2月11日の旧「皇室典範」(昭和22年5月2日廃止)は、憲法と同格の国家の根本法のひとつであったが――「政務法」と「宮務法」の二元的国法体系――、現行の皇室典範は日本国憲法の前提とする法律として制定されたものであり、単に旧皇室典範を改正したに過ぎないものではない。
名称が踏襲されたのは、皇室の尊厳に配慮し「一種の荘重さを与へる趣旨」(皇室典範審議会議録)からでたものである。その内容は、第一章「皇位継承」、第二章「皇族」、第三章「摂政」、第四章「成年、敬称、即位の礼、大喪の礼、皇統譜及び陵墓」、第五章「皇室会議」であり、皇室の国法制度面についてのみ規定し、皇室内部の問題についてはその自律に委ねられている。
皇室典範4条は「天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する」と定め、皇位継承原因を天皇の崩御に限定している。天皇の生前退位は、憲法上認められるのか。
退位制度に関しては現行の皇室典範制定の過程においても論議されたところであるが、①譲位による皇位継承という歴史的事実があること、②天皇の身分に不治の重患のある場合に退位を認めない理由が存在しないこと、③人間天皇の自由な意思を拘束することは不当であること――等の立場から肯定論も主張された。
しかし①天皇の自由意思と国家の基本制度が交錯するときは後者が優先すること、②天皇の重患若しくは重大な事故に際しては摂政の制度があること、③退位が政治的に利用されること、④天皇の意思により退位を認めることは即位の拒否の自由につながり憲法が定める世襲制度が脅かされること――等を理由に退位制度は採り入れられなかった経緯がある(昭和34年、第31回国会衆議院内閣委員会議録第5号6頁参照)。
憲法論としては、退位制度を認めるか否かは、恒久法として立法することをも加えて基本的には国民の総意を代表する国会の裁量権の範囲内にあり、立法政策の問題であり、皇室典範の定めに委ねられると解される。
しかし、天皇の意思でいつなんどきでも自由に退位し得るという制度や天皇の意思を無視し退位させるという制度は、憲法上大きな疑義が生じるのであって、制度的には、①天皇の自発的な退位の申し出、②国民代表たる国会の承認あるいは国会の委任を受けた皇室会議の承認、という手続きを内容とするものでなければならないと考えられる(高橋和之「天皇の『お気持ち』表明に思う」『世界』889号188頁参照)。
①の天皇の退位の申し出について言えば、それはあくまでも天皇自身の心情の発露としての私的判断であることが必要であり、そこに政府による政治的介入は微塵たりとも許されないものと言わなければならない。蓋し歴史が実証するように政府権力が天皇制を政治的に利用した場合、民主的なプロセスが崩壊の危機にさらされるからである。