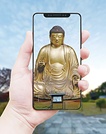近代仏教は「悪」とどのように向き合ってきたか(2/2ページ)
明星学園教諭 繁田真爾氏
だが、これらの著作を掲げて藤岡が訴えた方策は、大谷派本山には採用されなかった。さらに激務後の睡眠時間を削りながら2書を書き続けた代償として、藤岡は神経衰弱を病み、やがて結核に罹患した。教誨師の職も退かざるをえず、理想的な教誨制度を作り上げようとしてきた藤岡の奮闘は、ここに挫折を余儀なくされたのである。
その後約30年に及んだ療養生活では、打って変わって、藤岡は心静かで平穏な生活を心がけるようになった。晩年の藤岡は軽妙で文明・社会風刺も含んだ多くの漫画を描き、気ままな境遇を楽しむといった生活を送った。このように藤岡の生涯は、病気による挫折を間にはさんで、前半生と後半生の鮮やかな対照が特徴的なのである。
ここでは、監獄での教誨に挫折した晩年の藤岡が、「人生中最も必要なるものは自ら治むると云うこと」と断言していることに、注目しておきたい。犯罪者や囚徒など、「他者」をいかに治めるかということは、全く問題とされていないのである。
この言葉には、まずはみずからを治め、みずからを省みることが人生で最も大切であるという藤岡の信念が、実感に裏打ちされたかたちで簡明に語られている。誰よりも情熱的に監獄教誨を開拓してきた教誨師が、困難を力業で乗り越えようとして挫折した結果、最後は自己を治める道へと至ったことの意味は、大きいと考える。
私はこれまで、現役で活動している仏教教誨師の方々と会い、直接お話を伺う機会に何度か恵まれた。彼らは一様に慎み深い性格で、あまり多くは語られない方ばかりであった。また、被収容者たちと正面から向き合う宗教教誨には、やりがいとともに、様々な困難やジレンマもあるようで、それを心の奥底に澱のように抱えているように見えた。堀川惠子氏が『教誨師』(講談社、2014年)で克明に描き出したあの渡邉普相師の深刻な懊悩と、それはどこかで通底しているようでもあった。
人は「悪」を裁くことができるのか。人は誰かを思うように変える(矯正する)ことができるのか。死刑には反対だが、制度として死刑が現に存在する以上、死刑囚に最期まで寄り添う自分のような存在が必要ではないか――。
こうした教誨師たちのジレンマには、様々な表現や個人差があるとはいえ、いずれも私たちの社会が抱える根深い問題の一端が、凝縮されたかたちで表現されているともいえるのではないか。そしてそのジレンマは、少なくとも条件反射的に「凶悪犯には厳罰を!」と勇ましく叫びたてるだけで、埋め合わせることができるほど単純なものでないことは、確かであろう。
近代仏教の歴史を振りかえれば、清沢満之や近角常観をはじめ、人間の実存や宗教性を根源的に問い直そうとした仏教者のほとんどが、人間の「悪」の問題を正面から見つめ、生涯をかけて探究した。それはおそらく、キリスト教など他の宗教派でも同様であろう。
今日の犯罪更生や死刑問題も、彼らが原理的に探究した「悪」の問題に一度立ち返ってみることで、また別のアプローチから議論を提起してみることも可能ではないだろうか。自己と他者が同じ「悪人」であることを説いた清沢・近角そして晩年の藤岡たちの眼に、今日の死刑存廃論議は、どのように映るのだろうか。
裁判員制度が始まって8年、そして50%近い再犯率が深刻な社会問題として叫ばれる今日。ヒューマニズムの視座だけからではなく、人間学的な深みから犯罪や死刑制度を鋭く問題化し、発言していく固有の役割が、宗教者や宗教史研究者には求められているのではないだろうか。近代以降の仏教者や教誨師たちが、単純には割り切れない人間の「悪」の問題と格闘してきた歴史を知ればこそ、私は、正義の立場から「悪」を他人ごとのように切り捨てる死刑制度には、反対である。