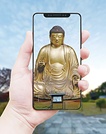生命の根源から考える農学 ― 人間と自然の関係問い直す(2/2ページ)
龍谷大農学部長 末原達郎氏
生命のことを考えるのは、仏教系大学の大きな使命の一つだと、私自身は考えている。もちろん、より哲学的な側面、仏教学的な側面から生命を考えることもできるであろう。
しかし、その一方で、非常に具体的な問題や日常的な問題から、生命を深く考えることもできるのではないかと思う。つまり、日々の食生活や農業を手がかりに、人間の生命の問題や農業の果たす役割を考えることもできると、農学研究者である私は思う。
われわれ人類は、生物体としての限界と宿命を併せ持っている。われわれは、動物であるから、自らの力で光合成を行うことができず、その結果、植物体を直接食べるか、植物体を食べた動物を食べるか、いずれかの方法をとらなければ生きていけない。いわば、生命を維持するために、他の生命に依存しなければならないという宿命を負っている。それだからこそ、人間には様々な生物と共に、自分たちの社会を共存させていく役割と責任がある。もし、人間だけが、他の生物に対して優位で、他の生物の利用権を握っていると考えるとすると、それは傲慢であり、間違っている。生命研究こそ、農学の中で学ぶに適した課題である。同時に、日常生活の中から人間と自然との関係性を問い直し、両者のいい関係を模索し実践していくことは、農学全体にとっても重要な課題となる。
同様のことが、農学研究者のみならず、一般の市民についても、言えることなのではないか。自らの食事を通して、その役割と深い連鎖とを考えると、それは自然における自らの存在や人間の社会のあり方を考え直し、再認識する機会になる。われわれが生きている社会の中で、どのように生命を存続させるのか、他の生命との関係をどのように見いだしうるのか、という問いに結びつく。
振り返ってみれば、現代文明ほど、こうした本来の人間の生命のあり方や食のとり方と、かけ離れたところで食料生産を行っている社会はないだろう。現代文明では、人間の食のために、すべての植物生産や動物生産が行われていると考えているが、それは正しいのか。
また、かつては、自分の家や近所の農家の片隅で栽培されていた農作物が食卓へとのぼり、食物として身体の内部に組み入れるようになっていたものが、今でははるか彼方から、場合によっては地球の反対側から、飛行機や船で運ばれてきたものが、われわれの食卓にのぼっている。農作物の生産者と消費者を結ぶ回路ははるかに長くなり、その全過程は、ますます見えにくくなってきている。
一方で、食料生産という過程が農業という自然と人間との共同作業である部分を通り越して、はるかに人工的になり、人間が一方的に自然を管理するものに近づき、利益を上げることのみを優先した仕事へとシフトしてきている。
こうした食と農をめぐる問題は、もはや単なる自然科学だけでは解けなくなっている。社会科学の側面をも含めて、今こそ総体としての科学が、明らかにすべき課題だと考える。また、それを通じて、さらにわれわれの社会もしくは文明そのものを、根底から考え直し、新たに造りかえていく実践的な側面を持った課題だと考えている。
龍谷大には、浄土真宗に基づいた五つの「建学の精神」がある。すべてのいのちを大切にする「平等」の心、真実を求め真実に生きる「自立」の心、常にわが身をかえりみる「内省」の心、生かされていることへの「感謝」の心、人類の対話と共存を願う「平和」の心、である。私には、いずれも農学の研究方向とぴたりと一致しているように思える。
おそらく、これからの21世紀には、食料問題も人口減少もさらに深刻になっていくだろう。われわれの社会が直面している問題は、はるかに大きく、われわれの文明の存亡を左右し、価値観の変化をも必要にしてくるようになると思えてならない。
農学を切り口にすることで、直接こうした問題の解決へと向き合っていけるチャンスがある、と私は考えている。若く可能性を持った多くの人材が、龍谷大の農学の分野から、羽ばたいていくことを夢見ながら、実践的な授業を行っていきたい。