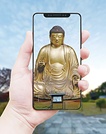教誨活動の歴史と課題 ― 「信教の自由」「政教分離」、両立模索(2/2ページ)
浄土真宗本願寺派 総合研究所研究助手 真名子晃征氏
二つ目の転換点が2003年に訪れる。当時の法務大臣の下、諮問機関として行刑改革会議がつくられ、「監獄法」の全面改正を含んだ改革へと進んでいくこととなる。
これより数年を経て、「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」(以下、「新法」)が施行される。そのなか「宗教上の行為等」として第67・68条において、被収容者の宗教上の行為の制限が解かれ、施設側も被収容者が教誨を受けることができるよう配慮しなければならないと定められた。これによって、法律上の根拠を欠いていた宗教教誨は公的に認められることとなった。
「信教の自由」とは何かを考える場合、大きく二つの見方ができるだろう。一方は「いかなる宗教も強制されない」自由であり、もう一方は「求める宗教を信仰できる」自由である。前者は国家の消極的態度によって保障されうる。しかし、後者はそれほど容易ではない。そこには、国家の側からの積極的な配慮や援助が必要となる。病院や軍隊のような特殊な環境では「信教の自由」を保障することが難しいとされる。そのため海外各国では、チャプレンと呼ばれる宗教者がそれらの施設に派遣されている。中でも矯正施設はその閉鎖性から保障が最も困難な施設であるという指摘もある。
「新法」の施行が、そのまま「求める宗教を信仰できる」自由へとつながったかどうかは現時点では判断できない。ただ、「いかなる宗教も強制されない」自由という旧来の方針から離れる、大きな改革であったと見ることができるのではないだろうか。
「新法」の施行によって、教誨師はその活動に法律上の根拠を得たが、いまだいくつもの課題を抱えている。
人材の育成はその一つである。龍谷大学矯正・保護総合センターが現役教誨師に行った調査によれば、教誨師となった経緯は、身内・知人からの紹介が90%を占めている。役割の性格を考えれば、その人物に関してよく知る者からの紹介となる事情は理解できる。ただ、このような後継が続けば、いずれ人材の確保に限界が訪れる。また、教誨師となるための統一された資格や条件が確立されていないことに対する不安の声も聞かれる。若手教誨師・女性教誨師が少ないことも課題である。
しかし一番の課題は、教誨師の存在自体が知られていないことにある。ほぼ時を同じくして成立した裁判員制度と比べると、「新法」への各種メディアの反応はあまりにも薄かったと言える。教誨は被収容者と教誨師の一対一の信頼関係やプライバシーの保護が前提にあるため、知ることができない情報も多くあるだろう。ただ、それを理由に十分な情報発信ができていなかったという教誨師の声も聞かれた。
しかし、それ以前に100年以上前から活動する教誨師について、これまで私たちは積極的に知ろうとしていただろうか。司法制度や社会のあり方について考えることは重要だが、被収容者や、そこに従事する人々の思いについて知ることを置き去りにしてきたのではないか。それらを知ることは、司法制度を考える上でも大きな意義を持つだろう。
(※1)矯正施設とは、犯罪を行った者を収容し、矯正のための処遇を行う施設をいう。刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所、婦人補導院のことを指す。このうち、刑務所・少年刑務所・拘置所の三つを刑事施設という。刑事施設は、旧来の「監獄法」では監獄とされていたが、新法の施行により改称された。
(※2)本稿は、葛西賢太・板井正斉編著『ケアとしての宗教』(明石書店、2013年)に「教誨師と更生活動」(金澤豊氏との共著)として寄稿した内容をまとめたものである。