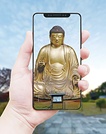変容する葬儀における「死の認識」 ― 直葬、家族葬、一日葬儀…(2/2ページ)
国立歴史民俗博物館准教授 山田慎也氏
自宅から出棺した後も、遺体に寄り添って葬列を行い、死者をあの世に送り出すために、供物や葬具を持って生者も行列をしていったのである。そして死者の世界とされる寺院や墓地において儀礼をすることで、死者をあの世に送り出すこととなった。つまり移動も寄り添いの過程であった。
昭和40年代以降、通夜が告別式化して自宅以外で行うようになっても、自宅搬送にこだわったのは、遺体への寄り添いを何とか維持しようとしたからと捉えられる。またこの頃から病院などの施設での死亡が増加し、昭和50年代初頭には自宅と逆転していく時期でもあり、寄り添いが断片化してゆくはじまりでもあった。
こうして寄り添いの断片化だけでなく、遺体の取り扱い自体を専門業者に依存するようになっている点も、死への接触が断片化し間接的になっていく要素となった。葬祭業者が納棺を行うなど遺体の取り扱いをするようになるのは昭和初期以降で、遺体の扱いが専門家へ移行していく要素は、公衆衛生的な観点もその背景にあった。
現在、病院によって清拭など死後処置が行われており、これによって民俗としての湯灌は消滅していった。清拭は儀礼ではなく明治期、欧米の死後処置法を導入したもので、看護書だけでなく主婦を対象とした家政書などにも記載され、次第に湯灌の代替と捉えられるようになった。
さらに昭和40年代になると、映画「おくりびと」のもととなった『納棺夫日記』(青木新門著)のように北陸や北海道などで納棺は専門化されていった。1980年代後半には、在宅看護用の移動式入浴システムを援用して、新たに「湯灌」とするサービスが開始される。そこでは、民俗としての湯灌を歴史的な正統性としながらも、それだけでは人々に必要性を感じさせないため、最後のお風呂という叙情的な共感を呼ぶことで全国に普及し、湯灌や納棺はより専門性の強い儀礼となった。
そこでは、遺体の肌を遺族に見せないようにすることが重視され、従来、遺族中心で遺体を直視した納棺も、主体性が業者側に移行し、肌を直視することを忌避した遺族はギャラリーとなり、時には触れることすら嫌悪感を持つようになっていった。
さらに遺体の保存処置であるエンバーミングもほぼ同時期から導入されるようになる。一般には公衆衛生が強調されるものの、実際の現場では遺体のやつれや損傷などの修復に最も関心が払われるなど、安らかな姿を作り出すように変化していった。
こうしてみるとかつての葬儀では、数日間自宅において日常生活を遮断して、故人に寄り添い遺体を繰り返し注視することで、濃密な時間を過ごして死を実感していったのである。
こうした過程では、次第に青白く弛緩し、時にはにおいなど身体的な変化も感じながら、死を受容する過程でもあった。しかし、納棺など専門業者に依存し、“理想の死”を作り出そうとしているのは、葬儀場の利用など接触が断片化していく分、何とか死を受け止めていこうとする営みとも捉えることができる。
だが、それでも、自宅空間はいつもと変わりなく途切れることのない日常生活の合間に、断片的な葬儀場での接触だけで、どこまで死を受容していくことができるのであろうか。
こうした状況は、死の尊厳性を理解できず軽くみてしまう人や、逆にいつまでも死を受容できず長期の悲嘆に陥ってしまう人など、両極端な認識を持ってしまうおそれが考えられる。急速な変容が生じている現代、どのように死を受け止めていくのか、意識的に考えていく必要が生じている。