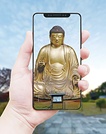内と外から見た神道 ― 自然への畏敬は世界に遍在(2/2ページ)
比較文化史家 平川祐弘氏に聞く
アメリカのプエブロ・インディアンが山々を崇拝しているのも日本人の神道的感覚と似たものだと感じました。自然への畏敬は世界に普遍的にあるもので、アニミズムというと西洋人は初期段階のものだと考えるけれど、その感覚は無意識の中に宿っているから逆に強いのではないかと思っています。
1980年にパリ大学で講演をするとき、ロンサールを神道的感受性で評釈したいとフランス人の同僚に提案したら、とんでもないと断られました。神道は戦争中の日本のナショナリズムの支柱となったものと見る西洋人は多い。
偏見が減ってきたのはアメリカですね。明治神宮は1945年4月、集中的に焼夷弾を落とされて本殿が焼き払われた。けれども神道敵視の間違いに気づいたのか、大統領も来日時に参拝するようになり、クリントン国務長官(当時)に至ってはお祓いを受けている。米国人記者からなぜお祓いを受けるのかと質問されて、日本の文化と伝統に敬意を表するためだと答えた。
神道を非合理的なものとする見方は日本人にもあります。『聖書』の天地創造神話というと何か尊いと思い込み、『古事記』の世界生成神話は荒唐無稽だと思うのはおかしいですね。自然科学的な見方に合致するのはむしろ後者ではありませんか。
自己認識は他者との関係で行われます。仏道が入ってきたから土着の宗教を自覚して神道と名づけました。和魂漢才、和魂洋才というときの「和魂」も外からの規定による自己認識で、固定的に定義されるものではない。アイデンティティーの内実は時代によって変化します。紫式部の「大和魂」と吉田松陰の「大和魂」では意味がちがう。紀貫之が『古今和歌集』の序文で「やまとうたは人の心を種として」と書いたのは漢詩との対比で言っている。
そのことに気がついていた本居宣長は、『古事記』や『日本書紀』に漢学が入ってくる以前の日本人の感じ方、考え方を調べるようになりました。しかし過度にアイデンティティーを追求するとナショナリスティックになって反動化します。自己を知るとともに他者を知るという精神の往復運動が大切です。
宗教はミッション活動を始めるとよその人にも教義を説かなくてはならないので自覚的になって説明しますが、神道は日本固有の宗教だから説明が足りない。クリスチャンは日本で人口1%以下でもミッション系の学校の数は多く教義について説明する人も多いのに対し、神道は「言挙げせず」で、神道とは何かという問いに日本人でもよく答えられない。けれども、このように国際化が進み、外国人と接触するようになると、明晰に神道を説明していく必要が生じます。
日本は島国で同質的な社会ですから、自己主張がそれほど強くない。原理原則を言うよりも「和を以て貴しと為す」でしょう。聖徳太子がなぜこの言葉を十七条憲法の最初に言ったかというと、大陸から仏教文化が入ってきたときに、それ以前の日本の宗教文化を排除しようとしたり争ったりせず、平和的に共存しようとした。和を以て貴しと為すというのはトレランス(寛容)が一番大事だということで、これからは世界的にそうしなければならないでしょうね。神道は自然環境を大切にする思想とも非常に近く、ポジティブに認められるところはたくさんあると思います。
比較文化史家 平川祐弘氏に聞く