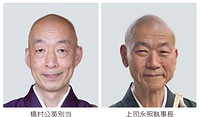良寛の観音信仰(2/2ページ)
元東洋大学長 竹村牧男氏
願我速知一切法、願我早得智慧眼、願我速度一切衆、願我早得善方便、願我速乗般若船、願我早得越苦海、願我速得戒定道、願我早登涅槃山、願我速会無為舍、願我早同法性身
(大正20巻、106頁下~107頁上)
この十大願が出る前ほどには、その観音が千手千眼を具えるに至った経緯も説かれている。母・秀子の観音信仰の内実を、その源泉に立ち返って究明しようとしていたのであろうか。
ちなみに、この『千手経』は、「ナムカラタンノートラヤーヤ……」という「大悲心陀羅尼」(「大悲呪」)の誦持を勧めることが主題となっており、この陀羅尼は禅宗でもよく用いられている。良寛は円通寺時代、いくどとなくこの陀羅尼を唱えていたことであろう。
なお、良寛が修行した光照寺も円通寺も本尊は観音菩薩であることに加えて、還郷後に親しんだ寺泊町の照明寺は、永承2(1047)年、弘法大師の聖観音を安置したのが始まりという。あるいは良寛が三条を訪れた時は常宿にしていたという、東裏館の宝塔院の本堂の本尊も、観世音菩薩であった。なお、この両寺ともに、真言宗智山派である。
実際のところ、日本の観音信仰の主たる流れは、『法華経』とともに、むしろ初期密教経典に説かれた十一面観音や千手観音等、また絵図の胎蔵曼荼羅の観音院(蓮華部院)に描かれた二十一の観音菩薩(その一例に馬頭観音、如意輪観音、不空羂索観音)等にある。確かに、日本における観音信仰の展開を詳しく知るには、『法華経』のみではまったく足りないことであろう。
そういうわけで、良寛は観音信仰にかかわる経論を広く学んでいたことは間違いないが、『法華讃』では観音菩薩の禅的な理解も示している。その讃は、次のようなものである。
「真観、清浄観、広大智慧観、悲観及び慈観あれども、無観最も好き観なり、為に報ず、途中未帰の客、観音は宝陀山に在さずと」
この讃で重要なのは結句、「為に報ず、途中未帰の客、観音は宝陀山に在さずと」である。「未帰の客」とは、観世音菩薩を尋ねようと補陀落山に向かっていて、まだ帰って来ない人を意味しよう。要は、外に観世音菩薩を求めてやまない人のことである。しかし良寛に言わせれば、観世音菩薩は、補陀落山にはいないぞ、というのである。それは、「無観」のところ、主客一如でおのずから働いているところのただなかにあるということである。
観世音菩薩が、自己の外にはいないということを、実は道元も言っている。道元は如浄のもとで大悟を得た後、近隣の各地を小旅行したらしい。その時、観世音菩薩がいますという、補陀落山にも寄ったらしい。その時、作った漢詩が、次のものである。
「聞思修より三摩地に入る、自己端厳にして聖顔を現ず、為に来人に告げて此の意を明らめしむ、観音は宝陀山に在らず」
これはまったく、良寛の意と同じことを歌っている。もちろん、道元のこの漢詩を承けて、良寛はあのような讃を作ったのである。良寛は道元に、500年のときを介して、ひそかに深く私淑しているのである。
もっとも、『法華讃』「観世音菩薩普門品」の最初の讃の最後には、「南無大悲観世音、哀愍し納受し給え、救世の仁」という句もある。この真意も問題ではあるが、ともあれ良寛は一方では観世音菩薩を、母親の薫陶を受けて、純粋に信仰していたことと思われる。良寛においては、内なる観音と外なる観音とは、決して矛盾するものではなかったのであろう。観音の大悲は、自己の内から自己に働くとともに、外なる他者を通じてこの自己に働きかけて来る。そのような霊性の構造を、良寛はよく理解していたのだと思われるのである。