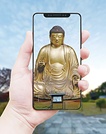災害時・地域防災での寺院の役割 ―大阪・願生寺の取り組みからの示唆(2/2ページ)
ジャーナリスト 北村敏泰氏
実際の災害時の教訓に基づき極めて緻密に設計されている。電気水道などライフラインが壊滅する中、開始時点で既に100人余りが校庭にいる。まずは体育館内のレイアウトと受付の設置を即決しなければならないが、館内の通路をどうするのかは避難者のプライバシーと全体の収容人数、受付が館内か屋外かは天候や感染対策との兼ね合いとなる。いったん決めたら途中変更はできない。断水の中でトイレも最重要事項だ。
避難者カードは「世帯主 58歳男性 全壊」「同 母親」「同 長女」などと年齢性別、国籍や抱えている事情が書かれており、その「事情」は「認知症」「妊娠中」「常備薬を失くした」「車椅子生活」から「ブラジル人」「テントを持参したが使っていいか」など千差万別。「イベント」も「後の安否確認のために名簿を作成するか」「毛布が来たが全員分はない」など簡単ではない事象ばかり。
参加者は、体育館に通路の線を引いて各家族を配置し、高齢者や体の不自由な人、あるいは病気の人をどの教室に入れるかに頭を悩ませる。救援物資の受け入れやペット対策、ボランティアや報道への対応まで迫られる。切れ目なく押し寄せ、それぞれに個別の困難な事情を抱えた避難者、予告なく次々と発生し、時間とともに刻々変化する多くの出来事に、ほとんどパニック寸前になる。
だが、両町内会とも参加者同士でリーダーを決め、事態に応じて素早く話し合って決定をし、仕事を分担してはすぐに対応することに努めた。実際に起こり得る災害を想像しながら真剣なまなざしで、1時間余りの演習はあっという間に終わった。
両グループでの意見交換では「家が部分損壊でも避難所入りを断れないが、人数に限りもあるし、どうすればいいか」「後から家族が来る、というケースであらかじめスペースを空けるのかどうか」「虚弱な高齢者だからといって孫ら家族と分離できないのでは」などと非常に実践的な課題が論議された。
総じて、「目の前」で困っている被災者への思いやり、想像力がカギと見られたが、とりわけ全ての被災者カードに「固有名詞」が付いていることは重要なポイントだ。「免震さん」「豪雨さん」などとあえて災害用語を奇異な姓として注意喚起しているが、決して「被災者一般」ではなく、それが「地域のあの町の誰それさん一家」という具体的イメージを呼び起こす、という意見があった。
演習途中、「地震で両親が死亡した5歳の姉〇〇ちゃんと3歳の弟□□ちゃんが逃げてきた」という状況に参加者は思わず胸を詰まらせたが、「この子らをよく知っているご近所さんのいる場所へ」と温かい心配りを示した。このような「個別性」への配慮はどの災害でも、また「障がい者一般」では決してない個々の医療的ケア者への寄り添いにも共通する重要な観点だ。
演習を逐次助言しながら進めた亀井教授は「相当に混乱しますが、この訓練での経験が実地では必ず役に立ちます」と。参加した町内会役員からは「とても具体的でよい体験になった。実際の災害時にはどこまでできるか、これからさらに勉強です」との反応があり、「身近なお寺でこういう集まりができるのはうれしい」との声も出た。寺で準備をし、両グループを回って作業の補助もした大河内住職は「白熱した内容で、それぞれの地域の課題も見えた。今後も経験や情報を互いに交換していきましょう」と締めくくった。
このワークショップによっても、地域防災の実際の在り方と、その中での寺の役割が顕在化したと言える。災害時に避難所となることを想定し、そのために非常食などを備蓄するといった内容にとどまらない地域密着のスケールの大きさが見て取れる。加えて、それは前記した第三のポイントにも密接する。
願生寺では以前から介護者カフェや子ども食堂、遺族の集い、「親なきあと」相談、「まちの保健室」や訪問看護ステーション運営など実に多彩な取り組みを地域で行ってきている。これが、直接防災とは結び付かなくとも、普段から「頼りになるお寺」「何かあったらあの寺へ」との親しみを醸成する結果を生じていることは間違いない。
東日本大震災の被災地でも、例えば岩手県大槌町で震災前から児童向けの「絵本読み聞かせ」といった取り組みをしていた寺院が避難所として力を発揮し、復興に向けても過疎化する地域のつながり回復のために全世代型食堂を続ける例がある。能登半島地震でも同様だ。願生寺のケースは、他の多くの寺院あるいは宗教施設にとっても一つの示唆となるのではないか。