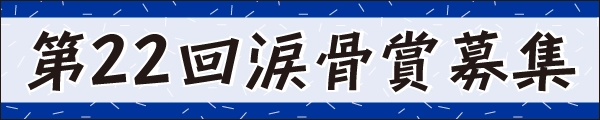曽我ははたして親鸞の往生論を誤解したか(1/2ページ)
京都大名誉教授 長谷正當氏
大谷大名誉教授の小谷信千代氏は『真宗の往生論』(2015年)、『誤解された親鸞の往生論』(16年)、および『親鸞の還相回向論』(17年)の3著書において、親鸞は死後往生を説いたのであって、したがって、曽我量深をはじめとする近代教学の現世往生論は親鸞の往生思想を誤解するものであると主張された。氏のこの見解を裏付けるものとして、近代教学の現世往生論は経典の誤読によるものであることは決定的であり、動かしがたいという評もなされている。しかし、小谷氏の見解とその評は妥当しないと思うので、その理由を述べ、曽我は「現生往生論」で何をいおうとしたかを改めて確認したい。
(1)小谷氏は、親鸞の死後往生論の論証に際して、『大無量寿経』の「本願成就文」の「即得往生」に親鸞が加えた注釈に対する桜部建師の解釈を究極の論拠とされた。そして、「近代教学を奉ずる人々の[親鸞は現世往生を説いた]とする誤解は、経文の紙背にまで視線を配って、凡夫であろうとも現生において真実の信心を得るならば、臨終時には往生が必ず得られることを論証するために敢行した、親鸞の苦心の読み換えの意図が見抜けなかった不見識に起因するものと考えられる」(『親鸞の還相回向論』45頁)と帰結された。
しかし、氏の論証には幾つかの疑問点があり、その結論は決定的とはいえない。
その理由の一つは、小谷氏が論証の究極的論拠とされている桜部師の解釈は、往生は死後であると前提した上で初めて成り立つ解釈であり、したがって、氏の論証は「論点先取」であって、実は詭弁の上に成り立っているということである。
二つは、曽我の往生論は、親鸞の注釈を桜部師とは逆方向に解釈することから導かれたものであるが、氏はそのもう一つの解釈に想到せず、桜部師の解釈のみに基づいて論証を展開されているため、その論証は独断的であり、論証として破綻しているということである。
三つは、曽我の往生論は、親鸞の往生思想を自己の身上において追究した「教学的思索」に裏付けられたものだが、氏は、文献学的読解によって教学的問題をも決定しうると考えられているため、氏の結論は一面的であり、その論証は空転しているということである。
これらの難点のため、氏の論証は無効となり、氏が苦心して構築された、威風堂々として完璧の感がある論証の壁は、そのままローマのコロシアムの如き遺跡と化するのである。
(2)真宗では伝統的に、往生は死後と決められてきた。信を獲たとき正定聚となって、往生は決定する。しかし、往生が決定したということは、往生したのでなく往生の約束が成立したということであって、実際に往生するのは死後である、とされてきた。
しかし、「信が決定したことは、信を獲たことである」とされるのに、「往生が決定したことは、往生を得たことではない」とは何とも奇妙な理屈である。「おたすけが定まった」ということは「おたすけを得た」ということではないか。それなら、「往生が定まった」ということは「往生を得た」ということである。ところが、真宗の伝統的な教えでは、往生は定まっても、往生するのは死後だから、「いま苦しんでいても、死ぬまで待っておれ」というふうに教えられてきた。しかし、そのような往生理解ははたして親鸞の教えに叶うものだろうか。「そういう真宗学が行われていては、わたくしどもの本当の救済が成立しておらぬと思う。それでは心は暗いと思う」。曽我はそう考えて、「往生が決定したということは、私どもに往生という新しい一つの生活が開けてきたということ」でなければならないと捉えた。これが、曽我が往生を現生に捉える根本的動機である。
したがって、曽我の往生理解は、経典の文字を、自己の経験との関わりを離れ、法律の条文を解釈するように、その意味を詮索するという具合に導かれたものではない。それは、親鸞の書いたものを、現代に生きる自己の身上において問い直すという教学的思索を通して導かれたものであることが見失われてはならない。そこからするなら、経文の上だけで、その往生論が正解か誤解かを決定してみたところで、実は意味がないのである。教学的読解は人間がいかに生きるかという問いと結び付くとき、それは時代に応じて変わるし、また変わらねばならない。