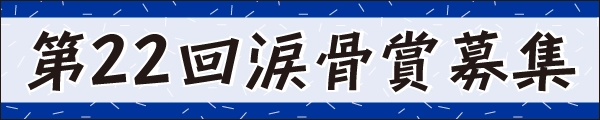なぜ僧堂で暴行事件が起きるのか ― 競争なき閉鎖性が暴力の土壌(1/2ページ)
慶応義塾大商学部教授 中島隆信氏
2015年4月10日付の『中外日報』に掲載された記事をご記憶の方も多いだろう。曹洞宗の僧堂で発生した暴行事件について、宗門サイドが僧堂の運営及び監督に関して不備があったことを認めたというものである。
私は法曹界の人間ではないので、法的責任の有無について物言う立場にはない。ただ、経済学者の立場としてその背景について何らかの説明をする必要があると感じる。なぜなら、どんな社会現象にも構造的な理由があり、それを明らかにすることによって同様の事件の再発を防ぐことができると思われるからである。
今回の事件を“タチの悪い”修行僧が起こした不祥事とみなし、トカゲの尻尾切り的な処理に終わらせるべきではない。もちろん、宗門もそのあたりのことは理解しており、僧堂の運営に対するガバナンスの強化を表明している。そうした対策は真っ当なものと評価することができよう。しかし、私はそこからもう一歩踏み込んで、そもそも宗教的な活動そのものがこうした不祥事を引き起こしかねない性質を有していると考えたい。キーワードは“閉鎖性”と“教育性”である。
宗教団体は特定の教義を信仰する信者たちが集まって作る自発的な組織である。そして教義の内容はそれぞれの教団で差別化されている。また、教義がほぼ同じであっても、浄土真宗の本願寺派と大谷派のように、仏壇の形式や作法などで差別化を図っているケースもある。その理由のひとつは、同じ教義ならばそもそも教団を分ける意味がなくなってしまうからである。もうひとつは、作法は優劣を比較できないので、競争を排除できるからである。実際、教団間の競争を避けるということは過去の経験に基づく智恵ともいえる。教義をめぐる争いは、優劣がつけにくいがゆえに感情的な宗教戦争につながりかねないのだ。
この競争を排除するための工夫が閉鎖性と深い関係にある。理解を容易にするため、民間企業を例に競争と閉鎖性の関係について考えてみよう。企業もオフィスという閉じた空間の中で同じ人間と時間を共有していれば必然的に閉鎖性が生じてくる。いわゆる“企業文化”というものだ。外部から不自然に見えることでも組織内では次第に当たり前になっていく。しかし、民間企業の場合、どのような企業文化を有していようと、最終的に製品やサービスが消費者に受け入れられなければ存続できない。たとえば、品質管理を怠り、決められたルールを遵守しなければ、欠陥商品が消費者の手に渡り、企業ブランドを大いに傷つける。そして消費者は他社商品を選ぶようになり、不祥事を起こした企業の経営状態が悪化するのである。つまり、民間企業は市場での競争に晒されているため、企業価値を下落させるような閉鎖性は事前に回避されるのである。
ところが、先に述べたように宗教は教義をめぐる競争をしない。特に、日本の仏教寺院では、檀信徒が境内墓地の永代使用権を取得していることが多いため、寺院間での檀信徒獲得競争はほとんど起こらない。また、僧侶についてもそのほとんどが世襲であり、外部からの新規参入者はマイノリティーである。それゆえ外部の優秀な人材獲得をめぐって教団間で競争するということも起こらない。このように、競争がないため、外部から見れば不自然なことであっても、他の教団との差別化という観点から正当化されやすくなる。冒頭の事件との関連でいえば、禅宗における修行の厳しさは他の宗派との差別化を図るための重要な要素でもあり、また外部とはあまり接点を持たない寺院関係者だけが集まる僧堂であるがゆえに暴力が常態化しやすかったと考えられる。