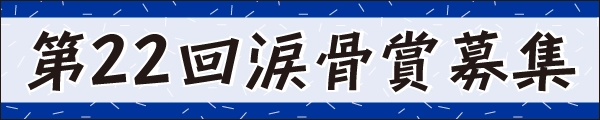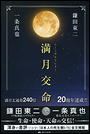高野山大学開学前史 ― 学僧・名僧が輩出した「学山高野」(1/2ページ)
高野山大図書館課長 木下浩良氏
高野山大学は去る10月17日に、創立130周年記念の慶事を迎えた。ただ、その淵源を辿ると、国内はもちろんのこと世界的にも最も古い1200年もの歴史と伝統を有する大学である。まずはこのことを第一に明記したい。
高野山大学の始まりは明治19(1886)年開校の古義大学林とするが、実は宗祖弘法大師空海の弘仁7(816)年高野山開創の時にまで遡られねばならない。昨年の平成27(2015)年に高野山は開創1200年を迎えたが、このことは高野山大学創立1200年の記念すべき年でもあった。本稿は、この高野山開創から古義大学林開校以前の、明治10(1877)年高野山大学林開校までの歴史を振り返りたい。高野山大学が今日あるのは宗祖弘法大師の御意志であり、大師以降の先徳の諸師の努力と労苦の賜物なのである。
高野山には二つの顔があるとは、仏教民俗学の提唱者である五来重先生が指摘されたことである。一つは弘法大師信仰としての顔、もう一つが「学山高野」としての顔である。弘法大師信仰としての御山の高野山については今更、紹介するまでもないが、「学山高野」のことは、意外なことに真言宗内においても知られていない。
そもそも、空海が高野山を開創された理由は後継者養成のためであった。朝廷は空海に年間の出家得度者3名を許した。その新人僧侶は、6カ年に及ぶ高野山住山をして、勉学と修行の日々を過ごしたのであった。以来、高野山からは幾多の学僧・名僧が輩出したのである。「学山高野」とされる所以はここにある。
この「学山高野」のことは近年、高野山大学名誉教授山陰加春夫先生の研究によりさらに明確になった。それが、イエズス会の宣教師フランシスコ・ザビエルが天文18(1549)年に鹿児島で書いた書簡にある記述で、高野山が中世日本の6大学の一つであると記されてあることである。他の5大学は、京都の五山官寺・根来寺・比叡山延暦寺・三井寺園城寺(または多武峰寺)・足利学校の五つであった。
高野山内の塔頭寺院はカレッジ(学寮)であって、高野山全体がユニバーシティーだった。高野山内の塔頭寺院の数は江戸時代の元禄以前で、1800軒以上を数えた。いわば、1800ものカレッジを有する大学が高野山であった。
明治維新の後に、高野山に近代的な学校が創建された。それが、高野山講学所である。開校は、明治2(1869)年と推定される。我が国が近代国家として再出発をした直後に、高野山上に近代学校が開校した意義は大きい。高野山の近代化は勤王僧の存在が大きかったものと考える。
この高野山講学所があった地点は、かつての大徳院があった場所で、現在の南院付近であった。学生は全寮制で、組織としては、下局と上局の2段階に分かれていた。下局は、20歳以下の僧侶と、20歳以上でも学力が劣る者と、外典(真言宗以外の典籍)を好む者が入らなければならなかった。
下局の構成は、さらに内典局と外典局があり、その両局はそれぞれ第一級・第二級・第三級との三つに分かれていて、全部で6級の段階になっていた。下局では主に素読が中心で、毎月試験があって、6級の全てに合格した者だけが上局へと進むことができた。下局の教師としては、外典に達者・悉曇に達者・声明に達者の各1名の都合3名がいた。まさに下局における教育は真言宗僧侶としての教養課程と初等・中等教育課程であったことが指摘される。この下局過程を終えて学生は上局へと進学するのである。上局では、真言宗所学の経・律・論の講義がなされた。要するに、真言宗僧侶としての高等教育をここで受けることになる。上局では6年を修学期間とした。
次に、高野山上でできた学校として、高野山小教院が挙げられる。慶応3(1868)年、明治天皇の名により天皇親政を宣言した王政復古の大号令の後、祭政一致の理念に基づき、明治政府において神祇官が復活して、国民に対する教化に乗り出した。しかし、見るべき成果はあげられなかった。一方廃仏毀釈の打撃を受けた仏教側は、新しい仏教界を所管とする中央官庁の設置を望んでいた。