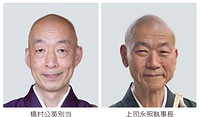教養と化した宗教の来歴 ― 宗教に親しんだエリート層(2/2ページ)
龍谷大アジア仏教文化研究センター博士研究員 碧海寿広氏
もっとも、宗教であれば何でもよかったわけではありません。寺社参詣のような庶民的な信仰活動や、素朴な地獄・極楽の実在論は、愚かな民による「迷信」として忌避されることが多かった。教養を求めた学生やエリートたちにとって、宗教とは基本的に、知的に洗練されたものである必要がありました。西洋哲学を通して再解釈された仏教や、近代社会を生きる人間のリアリティーに即した宗教の思想や実践が、そこでは希求されていたのです。
こうした教養主義的な宗教受容が息づく世界を目の当たりにしながら、やがて自らがその代表的な伝道者となっていくのが、倉田百三と和辻哲郎です。それぞれ、『出家とその弟子』(1917年)と『古寺巡礼』(1919年)という、宗教の教養化について語る上で決定的とも言える著作があります。どちらも教養主義の牙城とも言うべき岩波書店から刊行された、近代日本のベストセラー作品です。
『出家とその弟子』は、親鸞を主人公とする戯曲です。しかし、浄土真宗の教えを伝えるための作品ではまったくなく、仏教と西洋思想やキリスト教とがまぜこぜになった教えを語る親鸞や、その周囲の人間たちが織りなす群像劇です。そういった趣旨の作品ですので、真宗の「正しい」教義にこだわる向きからの批判の声も上がりました。けれど、著者の倉田は、この作品は自分の思い描く親鸞を書いただけだと、その種の批判をスルーしました。そして、真宗の教義的な正確さよりも倉田の示す独自の宗教的な物語のほうに引かれる多数の読者を獲得し、出版界での大成功を収めました。
一方、『古寺巡礼』は、和辻が友人と一緒に歩んだ奈良観光についてのエッセーであり、特に大和の古寺と仏像に関する記述を中心とする作品です。仏像と対面して恍惚となる著者の情熱的な文章が、読者の憧れや共感を呼び起こします。とはいえ、本稿にとって最も重要な点は、仏像を「美術」として捉えようとする著者のスタンスです。仏像は、拝むものではなく、観て楽しみ、あるいは歴史に親しむためのものである。本書に通底したメッセージですが、こうした発想は、仏像はあくまでも拝むものであると信じる亀井勝一郎のような敬虔な評論家からの反感を買いつつも、その後の古寺・仏像巡りのスタイルの一つとして、広く受け入れられていくのです。
宗教者やその思想をテーマとした本は読むが、その宗教の信者にはならない。古寺名刹や仏像を観るのは趣味だが、自分は仏教徒ではないと考える。日本人の間でそうした宗教との接し方が広まっていく上で、上記の2冊の本は、大きな影響を及ぼしたものと思われます。少なくとも、そうした風潮の伸張を象徴するような作品ではあったと思います。かくして宗教は教養と化し、今なお私たちの教養文化の一角に、宗教は存在し続けていると言えるでしょう。
と、ここで論を打ち切ってもいいのですが、しかし、最後にやや面倒なことを問うておきたいと思います。すなわち、「宗教を教養として受容する人々の宗教性とは何か?」。本稿で取り上げた倉田と和辻は、最期まで特定の宗教の信者として振る舞うことを避けました。様々な宗教思想や文化に触れて、それらを巧みに論じつつ、どこかで距離を置き続けることを忘れませんでした。しかしながら、幼少期に真宗信仰の濃厚な地域で育った倉田は、自らの死を目前にして、浄土の実在の有無が気になって仕方がなかったようです。和辻の天皇や日本文化に対する傾倒ぶりに、「宗教的志向の世俗化形態」を読み取る説がありますが(湯浅泰雄)、この説を敷衍すれば、彼の宗教性は常に世俗的な装いをもって発露されていたのだと強弁できるかもしれません。
宗教は一部では教養と化しました。しかし、人間は宗教から完全に自由な教養人として生きていくことが可能なのでしょうか。これは、掘り下げて論じるに足る問題であると思います。