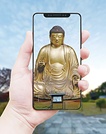心に寄り添うために発達障害を知る ― 全ての個性を認め合う(2/2ページ)
臨床心理士・浄土真宗本願寺派僧侶 武田正文氏
勉強に遅れがなく、おとなしい子の場合、アスペルガー症候群だと気づくのが遅れてしまいます。小学校高学年以降になると、なんとなく自分が他の子と違うことに気づき始め、疎外感や劣等感を抱くようになります。大きく傷つく前、できるだけ早い段階でトレーニングをすることでコミュニケーションの苦手さからくる躓きを防ぐことができるでしょう。
全般的な知的発達に遅れはないのに、聞く、話す、読む、書く、計算する、推論するなどの特定の能力を学んだり行ったりすることに著しい困難を示す状態をいいます。算数はできるのに、音読はどう頑張ってもできないということがあります。他の勉強はできるので、周囲の大人からは「怠けている」「もっと頑張ればできるはずだ」と思われます。
本人にとって何が苦手でどこに躓いているのかが分かれば、少し工夫をすることで学習がしやすくなります。文章の間に線を入れる、漢字に振り仮名をうつなど、ちょっとした工夫ですが、この工夫が見つかるかどうかで学習障害のある子にとっての勉強は違ってきます。
周囲の大人が発達障害に理解がないと、子どもの発達障害に気づかないままに傷つく体験を重ねてしまいます。本人は頑張っているのに、友達にも大人にも気持ちが分かってもらえません。傷つき体験が長く続くと、不登校やうつ、摂食障害、非行などの二次障害に至ってしまうことがあります。
大学生や社会人になってから発達障害が明らかになるケースもあります。学校のように一日の流れが決まっている状態では適応できていても、大学や社会に出ると、自分で柔軟に判断する必要が増え、うまく対応できなくなってしまいます。
発達障害の特徴を見ると「自分にも同じようなところがあるかもしれない」と思われたかもしれません。発達障害の特徴は特別なものではなく誰もが持っている特徴です。その現れ方が顕著であり、生活に支障がある場合に発達障害という診断がなされます。
得意・不得意が極端であったとしても、その特徴をうまく生かして生活できれば何の問題もありません。むしろ発達障害の特徴は、社会的に成功している人の中にも多く見られます。
多動で不注意ということは、裏を返せば、好奇心旺盛で行動力があり、新しいものを生み出すことに長けているかもしれません。こだわりの強さは、特定の分野での研究に向いているともいえるでしょう。発達障害を知るということは、一人ひとりの長所を大事にすることにもつながります。
発達障害を抱えながら心豊かに生きていくためには、全ての人の個性をお互いに認め、支え合うことが大切です。これは発達障害に限らず、一人ひとりが生きやすい社会を目指すと考えることもできます。仏教の目指す世の中にも重なるのではないでしょうか。
浄土真宗本願寺派では今年度、「思春期・若者支援コーディネーター養成研修会」を開催しています。ここでは、発達障害や性の問題といった若者の心の悩みに対する理解を深め、仏縁を頂く者として何ができるだろうかと模索しています。
発達障害に限らず、社会の理解の低さからくる誤解や偏見により、複雑になっている心の問題は多くあります。お寺という仏縁を頂く場所で、世の中の苦しみを知り、一人ひとりのいのちを本当に大切にするというのは重要なテーマでしょう。
お寺には様々な人がお参りになります。葬儀や法事には子どもや若者がいます。僧侶が関わるのはわずかな時間かもしれません。しかし、発達障害を抱え、自分の苦しみを誰も分かってくれない体験をしている子どもにとっては「このお坊さんはちょっと分かってくれた」という少しの経験が心の支えになるかもしれません。
発達障害に対する理解を深めながらも、発達障害にとらわれず、目の前の人を大切にするという姿勢こそが本当の「共感」ではないでしょうか。