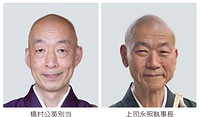いのちの終わりを見つめ合う~医療者と仏教者の対話(1/2ページ)
浄土真宗本願寺派延命寺住職 德永道隆氏
10月3日に浄土真宗本願寺派本願寺広島別院共命ホールにおいて、ビハーラ安芸主催の公開講座「いのちの終わりを見つめ合う~医療者と仏教者の対話~」が開催された。
全ての人に訪れる生老病死、そして現代は全ての人が何らかの形で医療に関わっている。その現状を踏まえて、いのちに関わっている医療者と仏教者が対話することによって、多くの皆様と、特にいのちの終わりについて見つめ合おうという企画であった。この公開講座は、両者がそれぞれの提言を出し、さらにディスカッションをするという内容であるために4時間に及ぶ講座であった。
荘厳な三帰依文の唱和に続き、まず仏教者の基調講演として、鹿児島の本願寺派善福寺住職であり、南風病院緩和ケア相談員で20年以上にわたり僧侶として病院に関わってきた長倉伯博氏が、「どうして坊さんが病院に?」と題して、病院に出向くことになった経緯や実際の患者や家族との関わりを話した。
医療者の基調講演としては、広島の緩和医療を推し進めた第一人者である、広島県緩和ケア支援センター長の本家好文氏が、「人生の終末期に寄り添う」と題して病院での患者を取り巻く状況の解説、多くの看取りを通じての提案である、看取りの文化の再構築など医療者として終末期に寄り添ってこられた現状を話した。
これらを受けて、パネルディスカッションでは龍谷大学特任教授の早島理氏をコーディネーターとして、訪問看護師の渡辺友規氏、そして筆者が登壇し、互いにいのちの終わりについて議論した。292名の参加者があり盛況であった。
筆者が緩和ケアの病棟に宗教者のボランティアとして関わって5年が過ぎた。毎週のカンファレンスへの参加や、患者・家族への介入も増えつつある。患者・家族への介入は、直接の依頼(僧侶と話がしたい)と主治医や看護師からの促し(この方には宗教的、あるいはスピリチュアルなケアが必要と判断)と半々くらいである。悩みながらも、「いのちを見つめる縁」を頂いている。
ただ、恐らく県内では医療者と協働してケアに当たっているのは筆者以外では耳にしていない現状がある。そこで、何か仏教者がケアをしていくことに対する広がりにつながる啓発活動が必要と考えていた。そこに、早島氏、長倉氏が昨年北海道で同様の講座を開かれた経緯があり、また薦めも頂いたのである。広島での開催に筆者も期待をした。
本家氏は、長年の緩和医療の中で多くの患者の看取りをされた。その見地よりこの度、宗教者や一般の方に向けた提言として、「看取りの文化の再構築」を掲げられた。それは次の5項目よりなる。
①「死」は、すべての人に起こる正常な現象である②死を迎えるまでの身体の苦痛を緩和するのが医療の役割であり、死を阻止するのが役割ではない③死を病院(医療者)から取り戻す④病院死が多く、看取り体験者が少なくなった。死後でなく、近親者に「看取りに参加」してもらう⑤宗教者も「看取りに参加」する必要がある。
死を忌避する文化への批判、患者・家族の主体的な看取りへの関わりの促し、そして、宗教者の参画と提示をされたのである。これを聞くと、宗教者への期待も感じられる内容であった。実際、この期待があって筆者は3年半ほど本家氏の勤める病棟に身を置かせていただいた。
しかし、ディスカッションに移ると様子は一変したといっても過言ではなかった。
筆者の発題を聞いた後での本家氏のコメントは、「やはり僧侶と一緒にやれる気がしない、話が説教調でなじめない」という意見があり、また訪問看護師の渡辺氏からは「何も病院に来なくても、お寺があるのだから地域での活動があるはずでは」という意見も出された。
これは、打ち合わせの時から言われていたことなので、私には驚きはなかったのだが、聴衆の前での意見であったため仏教者に対する何かの「憤り」を感じた。その背景に何かあるのだろうか。