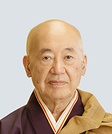公共空間と宗教 この20年から将来へ ― 大震災で存在感を増した宗教界(2/2ページ)
上智大特任教授 島薗進氏
これは宗教集団を開く働きと言ってよいだろう。宗教集団の外にある世俗社会が宗教的な働きの関与を求める時代になっている。世俗の領域でまかなわれると考えられてきた領域で、新たに宗教の役割が見いだされるようになっているのだ。医療や介護、自殺予防、災害支援はそうした例だ。
福祉国家の拡充が当然と考えられた時代には、国がお金を出して、世俗的な学知や技術を習得した専門職が役割を果たしてくれると期待されていた。だが、国家は福祉予算の削減を目指し、民間活力の発揮を求めるが、宗教はその重要な対象となる。そもそも世俗的な知識や技術だけでまかなおうとすることに無理があったことも気づかれている。死の看取りはそのよい例だ。
こうした状況は「ポスト世俗主義」とよばれる世界的な動向に対応している。1970年代頃までは、公共空間から宗教が撤退していくのが歴史の趨勢で、宗教はますます私事になっていくと考えられていた。ところが、社会の中で人々を支えまとめていく宗教の根強い力があらためて見直されるようになっている。
たとえば、生命倫理や環境倫理や平和の問題について、社会が宗教に基づく価値観を聞こうとする傾向が強まっている。人のクローンを作ってよいのか、再生医療をどんどん進めていってよいのか、生む子を選ぶ医療を受けいれてよいのかといった問題、また、エネルギー源として原子力に頼ることは倫理的に妥当なのかといった問題だ。また、兵器を売りつけて儲けるような産業を育て、それに寄与する科学を奨励することを認めてよいのかといった問題だ。
欧米ではこうした問題に対するキリスト教の見解はつねに参照されるものになっている。いのちや平和について「倫理」が問われるとき、宗教からの声は欠くべからざるものなのだ。2011年の福島原発事故後に、原発の将来を決めるためにドイツ政府が設けた委員会は「安全なエネルギー供給に関する倫理委員会」と名づけられていた。そして、その委員会には宗教界からの委員が一定の割合を占めていたことが思い起こされる。
日本でもこうした傾向は次第に目立つようになっている。たとえば、福島原発事故後には全日本仏教会が「原子力発電によらない生き方を求めて」という宣言を出した他、多くの教団や宗教者が脱原発の方向性を示す意思表示を行っている。また、平和という主題については、2014年7月の集団的自衛権を認める閣議決定について多くの教団や宗教者がそれを批判する意思表示を行った。
もっとも宗教界は脱原発や軍事活動の拡充に対して反対する動きという方向で統一されているわけではない。原発推進を掲げ集団的自衛権容認を推し進めてきた安倍政権も宗教勢力に後押しされていることが注目されている。安倍政権では閣僚の8割ほどが日本会議に属しているが、その日本会議の役員には宗教教団関係者が数多く名を連ねている。首相の靖国参拝を求める立場や、経済発展重視の政策や国家主義的な政策を支持する側にも、宗教が大いに関与しているわけである。
世界各国では原理主義やナショナリズムに親和的な宗教勢力が、大きな政治的影響力を及ぼす例が少なくない。イスラーム圏の国々、アメリカ合衆国、イスラエル、インドなどが念頭に浮かぶが、日本でも宗教的ナショナリズムの影響力が強まっていることに注意が必要である。また、宗教集団が自集団の利益を重視する形で政治に関わる例も見られる。
公共空間に対する宗教の関与が深まるなかで注意すべきことは、宗教が結束を重んじるあまり排除の機能をもつ傾向である。内と外を厳しく区別し、外に対する攻撃性を強める傾向は宗教とナショナリズムの双方にしばしば見られるものだ。このような傾向が強まると、宗教は多元性を尊ぶ開かれた公共性のあり方を阻害することになる。日本の公共空間における宗教の関与についても、この点をくり返し問い直す必要がある。