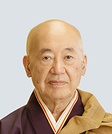社寺拝観制度の成り立ちと変遷 ― 拝観料、明治初頭の博覧会に起源(2/2ページ)
相国寺史編纂室研究員 藤田和敏氏
1898(明治31)年以降、内務省令第6号による拝観制度は第2次世界大戦の終結まで継続された。戦前の社寺拝観は公権力の管理下に置かれていたのであり、拝観を許可していた地方行政は社寺に対する支援ばかりを意図していた訳ではなかった。
そのことを示す一例として、1934(昭和9)年に京都市が導入を進めた京都拝観社寺組合共通拝観券について述べておきたい。
京都市が定めた「京都社寺共通拝観券取扱手続」には次のような取り決めがある。
①拝観券の種類を50銭券12枚綴りと1円券24枚綴りとする(第2条)。
②各社寺における拝観券の所要枚数は個別に定める(第3条)。
③拝観券による社寺の収入は拝観券1枚につき35銭とする(第4条)。
④拝観券の発売は日本旅行協会京都出張所・市内乗入郊外電鉄会社・市内旅館業組合に委託する(第9条)。
この規約に基づき、京都市は鹿苑寺に組合への加入を勧告したが、鹿苑寺は次の理由から不参加を回答した。
①拝観組合に加入すれば、一般拝観料が3割減少する結果となる。
②社寺門外において土産物的に社寺拝観券を販売することは、神聖観念・信仰観念をもって参拝すべき社寺として寒心に堪えない。
鹿苑寺による②の回答からは、拝観に対する行政と社寺との認識の相違が如実に表れたと評価できる。1898(明治31)年内務省令第6号が、社寺来訪者の目的を参拝と観覧の2種類に分けて、後者を目的とする者に対してのみ料金の徴収を認めたことからも明らかなように、行政は拝観を宗教性が存在しない単なる文化財の鑑賞行為と見なした。
それに対して鹿苑寺は、宗教財である仏像・庭園などを拝観することは宗教行為に他ならないと考え、京都拝観社寺組合への加入を拒否したのである。
この論点は、昭和60年代に導入が進められた古都保存協力税をめぐって京都市と京都仏教会が展開した論争においても、両者によって繰り返し主張された。
以上に述べた拝観制度の変遷は、従来検討されてこなかった問題である。近現代の仏教教団制度については未解明の点があまりにも多い。今後さらなる調査研究を進めていかなければならないと考える。
なお筆者は、相国寺教化活動委員会から5月に刊行が予定されている『宗門と宗教法人を考える―明治以降の臨済宗と相国寺派』で、明治初期の廃仏毀釈・上知令から昭和期の古都税反対運動に至るまでの臨済宗と相国寺派の歴史的展開について検討している。