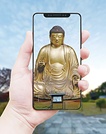中世の『日本書紀』研究を担った学匠たち(2/2ページ)
弘前大准教授 原克昭氏
では、ここで学匠による『日本書紀』注釈研究の内実を知る一例として、先述の良遍『日本書紀聞書』の一齣を垣間見ることにしたい。『日本書紀聞書』ははじめに第1条「一、神道名字事」以下、事書形式で神道論が展開され、その末尾には「已上、由来之事」とある。『日本書紀』の解題・大意を述べた「由来」にあたる。
つづいて「入段料簡之事」として、まず「日本書紀巻第一上」の題号を一字ごとに解釈した上で、『日本書紀』本文劈頭の第一文字目「古(いにしへ)」以下、語句を摘出し注釈が施される。つまり『日本書紀』の講述方策として、「由来」―「題号釈」―「入段料簡」という構成が見て取れる。この構成のうちに、『妙法蓮華経』など仏教経典を講ずるに際して、「大意」―「釈名」―「入文判釈」に沿って解釈する「三門釈」の手法を認めることは難くない。
ただし、それは経典からの単なる模倣や擬態ではない。本来は国書・外典に相当する『日本書紀』を、いわば経典類に準ずる《神典》として認知していた学匠たちの学問態度を見出したい。
このように、中世の学匠たちによる『日本書紀』の注釈研究の多くは、講述―伝授を経て筆録された聞書・私見聞といった形態をとる。それは、ひとえに神話研究が単なる机上の座学ではなく、仏教の灌頂儀礼に倣った神祇灌頂(神道灌頂・日本紀灌頂ともいう)を媒体としていたからにほかならない。
神祇灌頂という営為は、授者―受者の双方が神話世界を感得し追体験する宗教的実践であり、神話言説と儀礼空間が相互作用した注釈的営為でもある。その過程でもたらされた宗教言説が、仏と神を重畳させた仏神論であり、神代という古(いにしへ)と中世という当時(いま)をつなぐ神仏習合論であった。
伝授・講釈の現場から言説が喚起され、注釈言説が信仰空間を形成する。こうした『日本書紀』をとりまく中世特有の宗教思想環境のうちに、注釈的営為のリアルなまでの動態が再現されている。
さらにいえば、中世諸学匠たちのまなざしは、江戸時代の国学思想に顕著な神話世界に「古代」を見据える視座とは異なっていた。中世の学匠にとって『日本書紀』の神話言説は当時(いま)と断絶した遙かなる「古代」の神話ではなく、むしろ悠遠なる神代から中世にいたるまで連綿とつづく共時的世界としてあった。そこでは単線的で連続的な通時性ではなく、「心」という回路を経て古(いにしへ)と当時(いま)を仏神論で介してつなぐ、輻輳的で重畳的な共時性が追究されたのである。
『日本書紀』のうちに、中世を生きる「我等」の拠り所と帰趨すべき「心」の原像を見定めようとした、一種の実践的な宗教哲学を読み取ることもできるだろう。その具体相は、各地の主要寺院聖教として伝えられた各種の「神祇灌頂壇図」が、したたかに物語るところでもある。
中世にあって、『日本書紀』は決して神道家の専売特許などではなかった。『日本書紀』を基調とする多彩な宗教言説と信仰空間を構築させるには、仏教学に根ざした教義と儀軌を必要とした。まさしく、それを可能たらしめた中世の学僧たちの叡智には測り知れない奥深さがある。