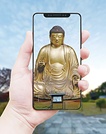過疎地神社の現状と今後 ― 過疎地寺院問題≪10≫(2/2ページ)
モラロジー研究所研究センター主任研究員 冬月律氏
次に、氏子・崇敬者については全国的に減少傾向にあるなか、過疎地域ではほぼ半数(46・9%)の神社は氏子数「300人未満」であることが明らかとなった。筆者の神社調査の結果からも、前記地域(人口は約1万3千人)に鎮座する神社全体(103社、法人)の氏子数は9割以上が300人未満であった。今後も氏子減少が止まらない状況下において、過疎地神社の運営護持はすでに厳しい局面を迎えている。
さらに、神社の収入については本庁調査によると、過疎地神社の年間収入でもっとも多かったのは「10万円以上100万円未満」(36・1%)で、次いで「100万円以上300万円未満」(21・7%)、「10万円未満」(12・8%)の順となっており、全国の過疎地神社の7割を超える神社は300万円未満の低収入で運営されている。収入の内訳を神社全体でみると、主たる収入源の上位3位は、「氏子費」(38・8%)、「祈願に際しての初穂料」(18・9%)、「祭礼に際しての奉納金」(11・6%)といった宗教活動によるものである。
筆者の調査からも同様の結果が得られた。ただし、実際の神職の生計との関係でいえば、過疎地神社の神職は、賽銭やお札をはじめ、祈祷料のような神社での宗教活動による収入では生計を立てられず、兼職を余儀なくされているケースも少なくない。氏子数十戸の小規模神社の場合、年に数回の祭典にかかる費用は氏子費と祭礼時の奉納金から賄われており、神職への謝礼も経費に含まれる。この謝礼が神職の主たる収入源となるのだが、参拝する氏子に現役世代が少なく、年金で生活する高齢者が多い。年間経費20万円以下の神社を数十社兼務しても、神社からの収入だけで神職自身と家族の生計は厳しい。「兼務神社が多い」や「専業」などは必ずしも安定した生計を保証する要件ではないのである。さらに、このことは将来の神職の後継者問題にまで影響を及ぼしているのだ。
過疎地神社の収入状況による問題はほかにもある。安定的な収入の確保が難しい、または不可能に近い神社は、境内の造形物の老朽化の修繕の見通しが立てられない。そのような状況下で、近年多発する自然災害となると、もはや太刀打ちできる体力が神社には残されていないのである。
神社界がこれまでに取り組んできた過疎対策は、「実態調査」「モデル支部対策」「教学研究大会」「連絡協議会」などがある。とくに過疎地域の実態調査は、神社本庁の「過密過疎地域の神社実態調査」(1968年)、「過疎地帯神社実態調査」(72~76年)のほかに、全国の神社庁でも行われており、その概要は報告書や業界紙の『神社新報』からも確認できる。
しかし、多くの過疎地神社では過疎化、少子高齢化の進行に伴う地域間格差や後継者問題の深刻化、不活動神社の問題が今でも叫ばれている。こうしたなか、2016年に神社本庁は新施策として「過疎地域神社活性化推進施策」を施行した。この施策による推進事業は、振興・活性化の視点を個々の神社から地域全体に広げることで、地縁や血縁、氏子と非氏子といった分断的な関係性に固執せず、多様化した社会と神社を結びつける可能性を見出すことが期待されている。
過疎化・人口減少が進む苦しい状況において、約7万8千神社(神社本庁包括法人、17年12月時点)の約3割の神職(うち宮司は半数)は「兼務」というやり方で、圧倒的多数を占める過疎地域の神社を消滅する事態から回避させてきた。そのため、一般的に神社は村落が消滅しない限り、年中行事や通過儀礼を通して細々と護持可能であるとみなされている。
かつての家を基盤にした日本社会において、寺院と神社は家の宗教と地域の宗教として社会の紐帯の形成と維持に大きな貢献をしてきた。それゆえ、檀家の減少と寺院の存廃問題への危機がすでに現実として表れ、過疎地域の寺院が淘汰される状況下で、寺院と同じ問題を抱えている神社だけが生き残ることは考えられない。
今後も過疎地神社を取り巻く状況は益々厳しくなることが予想されている。将来の護持運営に備え、「神社は過疎に強い」という根拠のない考えを正し、現実を直視した姿勢と地域性に見合う対策が、神職と氏子、ひいては地域に求められている。