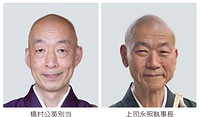実範の中川寺成身院 ― その密教寺院としての意義(1/2ページ)
京都大准教授 冨島義幸氏
醍醐寺(京都市伏見区)に伝わる国宝「醍醐寺文書聖教」の中に興味深い一巻の伝法灌頂――阿闍梨の位を与えるとき、師から弟子に密教の法を授ける儀礼――の指図(四一六函一三六号指図)がある。
前半には会場の分からない伝法灌頂の指図が、後半には治承3(1179)年、醍醐寺三宝院灌頂堂で勝賢が寛昭に授けた伝法灌頂の指図が収められている。後半についていえば、三宝院は醍醐寺の最も中心となる院家で、勝賢はこの時、醍醐寺座主であった。この伝法灌頂は、後世の醍醐寺流の伝法灌頂の規範となる仏教史上重要な儀礼である。これと合わせられているのだから、前半も何か重要な寺院のはずだ。
前半の指図に描かれた仏堂は大日如来を本尊とし、その前に向かい合うように両界曼荼羅を懸けている。この組み合わせは醍醐寺三宝院と同じである。この指図の仏堂を求めて密教の仏堂を調べていくと、実範が天永3(1112)年に創建した大和の中川寺成身院(奈良市中ノ川町周辺)が浮かび上がってきた。
実範や中川寺成身院は、一般にはあまり知られていない。しかし、中世仏教の研究に携わる研究者ならば誰でも知っている、中世の仏教を語るうえで重要な僧・寺院である。実範は、これまで天台・真言双方の流れをくむ念仏者として、また鎌倉時代における奈良を中心とした戒律復興の先駆者として語られてきた。こうした事績が重要なことはいうまでもないが、実範の仏教の基底が真言密教であったことを見落としてはならない。ただ、真言密教僧としての実範の事績は、同じ時代に活躍した覚鑁の影に隠れてしまっているようにも見える。覚鑁は院政期に真言密教を隆盛させたことから、また高野山に大伝法院を創建した新義真言宗の開祖としても著名である。
実範は興福寺で法相を学び、小野曼荼羅寺――現在の隨心院(京都市山科区)――で厳覚から小野流の真言密教を伝授された。さらに、実範は高野山の教真にも密教を、比叡山の横川で明賢から天台も学んだという。実範が興福寺で学んでいたのは、範俊が興福寺権別当だった頃と考えられているが、範俊は小野曼荼羅寺の成尊から密教を学び、実範の密教の師である厳覚は範俊の弟子であった。実範は範俊と共に、鎮護国家の密教法会である後七日御修法に出仕している。平安後期の興福寺に、小野流の密教を受け継ぐ僧侶がいたことは注目に値する。
中川寺成身院は実範の仏教を反映し、法相・真言・天台を兼学する寺院であった。今日廃寺となっているが、かつては成身院を中心に地蔵院・十輪院など多くの院家を備え、大規模な伽藍を形成していたと考えられる。成身院の経蔵には多くの聖教が集積され、そこで書写された聖教が京都の高山寺や滋賀の石山寺、愛知の真福寺などに伝わっている。中川寺は仏教教学を学ぶ拠点でもあった。
実範は忍辱山――現在の円成寺(奈良市忍辱山町)――にいたとき、花を採りに中ノ川に行き、その勝景にひかれ中川寺成身院を創建したと伝えられる。中ノ川は、奈良県と京都府にまたがる閑寂な山林の中にあり、今日でも周辺には円成寺をはじめ、浄瑠璃寺(京都府木津川市)・岩船寺(同)など美しい伽藍が残っている。
では、中川寺成身院はどのような建築だったのだろうか。覚鑁創建の高野山大伝法院を根来(和歌山県岩出市)に移転した頼瑜は、『真俗雑記問答鈔』に中川寺成身院は高野山大伝法院とともに、青龍寺を写したものであると記している。青龍寺とは、空海が中国で恵果から密教を学んだ寺院である。空海が創建した密教空間である宮中真言院や東寺灌頂院は、東の胎蔵界、西の金剛界からなる両界曼荼羅を向かい合うように懸けていた。後七日御修法が修されたのは、このうちの宮中真言院である。頼瑜によれば中川寺成身院には両界の仏台を設けていたといい、両界曼荼羅を懸ける空間であったことが分かる。