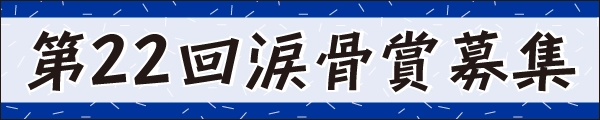高野山奥之院の大名墓 ― 憧れの聖地、全国の半分弱が造立(1/2ページ)
高野山大図書館課長心得 木下浩良氏
真言宗の聖地である高野山登山をして、根本大塔などの仏堂が立地する伽藍と、弘法大師空海の御廟がある奥之院を参詣しない人はいないであろう。
特に、御廟へと導く奥之院の参道の両脇にある、見上げるほどの大型の五輪塔が立ち並ぶ様には、誰もが驚くであろう。それらは大師信仰そのものを象徴する遺物である。そのモニュメントともいうべき大型の五輪塔の大半は、江戸時代初めに造立された、戦国時代に生きた武将たちの供養塔である。さらにそれを取り囲む石塔群はその武将の夫人やその末裔や家臣らが建てたものであったりする。
高野山を紹介する一部の案内書にはそれら石塔について、「徳川幕府の政策で、譜代大名の墓は小さく、外様大名の墓は非常に大きい」とか、「徳川家に倣って諸大名も墓石を建てた。徳川家が数ある菩提寺の一つとして高野山を定め、奥之院に供養塔を建てたのに倣い、全国の三百の諸大名も、供養塔を建てるようになったと伝わる」と記されているのを見るが、実はそれらは全くの俗説であって、石塔の大小は徳川幕府とは関係がない。石塔の大小は、建てた造立者の意向であった。領地の石高によって、石塔の大きさが比例する訳でもなく、1500石取りの大名の家臣であっても、大型の大名墓に匹敵する五輪塔を造立しているケースも見いだされる。
諸大名が高野山奥之院に石塔を造立したことも、徳川幕府に倣ったものとはいえない。徳川将軍家の石塔は奥之院には無く、江戸時代において御廟橋付近には将軍家代々の年忌供養をした五輪卒都婆が造立されていたが、それらは全て木製であり、高野山側が年忌法要の後に立てたものであった。
その上、全国の全ての大名が奥之院に石塔を造立している訳でもない。現状では全国の大名家中、約半分弱の大名家による石塔の造立が確認されている。この大名家が奥之院に石塔を造立する、しないの性格の相違はどこに所以するのかは、今後に残された研究課題である。
石塔造立が無かった一例を挙げると、肥後一国の領主となった加藤清正が挙げられる。清正の子忠広の石塔も、現状では確認できない。加藤家はその2代で断絶となるので、石塔造立には至らなかったという見方もできるが、私見を言えば加藤清正が熱心な日蓮宗信者であったことを指摘したい。いずれにしても、奥之院の石塔造立には個々の大名家のさまざまなお家事情を思わざるを得ない。
ただ、全国の半分程の大名家が高野山奥之院に石塔を造立したということは、それだけでも高野山が大名家にとって憧れの聖地であった事実には間違いない。なぜなら、全国の聖地や寺院などで、これほど大名家が石塔を造立するところは他では無いからである。
では、いつごろからこのような大型の石塔が造られ始めるのであろうか。そのことを考察する上で第一に挙げねばならない奥之院の石塔として、石田三成の五輪塔を紹介したい。総高267センチの砂岩製五輪塔である。銘文は、地輪正面に、「天正十八庚寅、宗応逆修、三月十八日」とある。「宗応」とは石田三成の法名である。銘文によって、三成は1590(天正18)年に逆修をして、高野山奥之院に自身の石塔を造立したことがわかる。
逆修とは、生きているうちに自身の葬儀をすることである。三成の生年は1560(永禄3)年とされているので、高野山に五輪塔を造立した時の三成の年齢は30歳である。この頃の三成の所領は4万石程度であったとされる。まず、30歳という壮年期に逆修をしたことには注目されるが、問題はこの三成の五輪塔が天正18年当時では、高野山奥之院において最大規模の石塔、ということである。
4万石という財政面もさることながら、石田三成の並々ならない大師信仰者としての一面を今に伝えるものと考える。三成は後年、奥之院の御廟に向かって右側に亡き母の供養のために経蔵を建立し高麗版一切経を納めてもいる。
天正18年当時といえば、豊臣秀吉による天下統一が目前で、相模国小田原城攻めに出陣した時にあたる。ようやく戦国時代から全国統一がなされる頃に、この石田三成の五輪塔は造立されている。
それまでの奥之院における石塔は、総高60センチ程度の五輪塔や、方柱状の一石の石柱を五輪塔形に刻出した、これも40センチから60センチ程の一石五輪塔の造立が主流であった。天正18年当時の奥之院の様子を想像すると、現状とは全く違って、1メートルにも満たない石塔群が群立する中に、この石田三成の五輪塔は3メートルにならんとする大きさであって、ひときわ目立っていたと思われる。やはり世情の安定の中で、高野山の石塔も大型化したことが指摘されるのである。