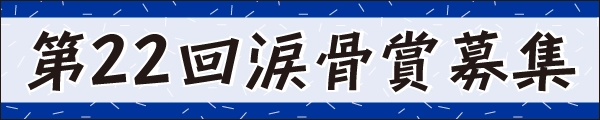臨床宗教師研修の体験から学ぶ ―「良かった」の気持ち共有(1/2ページ)
傾聴ボランティア「聞き屋」代表 吉田敬一氏
私は現在、大阪の寺院で平僧として法務に勤しみながら、兵庫県内の緩和ケアホスピタルで、傾聴支援ボランティアとして活動している。終末期医療や、終の棲家と言われる高齢者施設の只中に僧侶がいることは、葬式仏教の観点からとてもデリケートなことと十分承知の上で活動する、その訳となぜそこに至ったかを、私の体験に基づいて述べたい。
私の人生、順風満帆とは言い難い。中でも私が一番涙したのは、重い障害を持っていた長女が亡くなったことだ。このことは私たち家族にとって、まさに言語に絶する出来事だった。長女亡き後は、自らの悲嘆を埋めるが如く、他人の悲嘆に寄ろうとしていた。
その後、毎日の法務に没頭しながらも、ボランティア講習を受け、ホームヘルパー2級を取得し、市の紹介で作業所と高齢者施設に傾聴支援活動と称して通い始めた頃に、東北で大震災があり、居ても立ってもおられず、災害ボランティアとして宮城県石巻市と南三陸町に向かった。
ある時、寺の仲間が私の名刺を作ってくれた。そこには「聞き屋」という名称がデザインされていた。すぐに「駅前」が浮かび、とりあえず法衣のまま「聞き屋」の看板を首から下げて立ってはみたが、「見ず知らずのお前になぜ話す!?」と言わんばかりの視線を浴び、目の前を素通りして行く厳しい現実があった。
高齢者施設での傾聴支援ボランティアは市の紹介のため、宗教的な行為は禁じられていたし、もちろん私も同意はしていたが、それでも自前のエプロンにお坊さんイラストのアップリケを貼り付け小さくアピールした。しかしこの点においては、私の経験や宗教者としての特性を活かすことが出来たら、もっと被支援者さんに寄り添うことができるはずだとの思いを強め、焦っていた。
そもそも、亡き長女の存在が、私がこのような活動をする理由にある。長女は生前、医療、福祉、行政など多くの支援者によって生きる機会を与えて戴いた命だった。長女は重い障害を持って生まれ、困難な手術を乗り越え、地域の小学校へも入学できた。その小学校へもボランティアの看護師さんが付き添って下さったことは、今でも本当に感謝している。
このような多くの支援に報恩謝徳の行動で報いる、それが活動の主な動機である。被支援者と支援者、人が人を支える、人の心が人の命を支える。私は何よりも大切な長女の命で、この教外別伝の教えを深く自身に刻み込むことになった。
私なりの支援活動を模索する中で、「死期が迫った患者や、遺族への心のケアを行う『臨床宗教師』を東北大学大学院・実践宗教学寄附講座で養成」と書かれた記事を見つけた。臨床宗教師という名称が頭の中に焼き付いた私は、迷うことなく、臆することなく応募する決意を即固めた。
第1期受講生として、石巻に降り立った初日、降りしきる雨の中、行脚から研修は開始された。私はその行脚中に不思議な体験をした。ない髪の毛が逆立ち、全身が震え、涙が溢れる。「娘が付いてきてるのか!」。漠然としていたが、娘とのつながりを感じ得たのである。
研修では座学を主に、グループワーク、ロールプレイと、朝から夜まで息つく間もない内容の上、一日の講座を終えた後も、異なる価値観の宗教者たちと交流することが何よりだった。実習においては、「傾聴移動喫茶カフェ・デ・モンク」に参加し、実際に被災者が暮らす仮設住宅の集会所に伺った。実習に先立ち、主宰する金田諦應先生が「本来このような傾聴は地元の宗教者がすべきこと」と仰られた意味の一端が直ぐに理解できた。
一つは方言と訛りの壁である。二つ目には、地域の町名や建物名、商店名などの情報だ。これが理解できなければ会話が動いていかない。それでも相手様は、想像を絶するお話を語り、私は今までにない程に全身全霊でお聞きする。すると、話して良かった、お聞きして良かったとお互いにそう思える感覚が起こる。良かったと感じた気持ちの共有だ。これは研修で得た、傾聴における重要な学びである。
研修の一つ「宗教間対話、日常儀礼の体験」で、私の宗教者としての生き方を揺さぶる言葉と出会った。それは新約聖書「マタイによる福音書第6章」の「施しをする時、祈る時」である。この教えを示してくれたのは、同じ研修生で韓国から来日した宣教師だ。